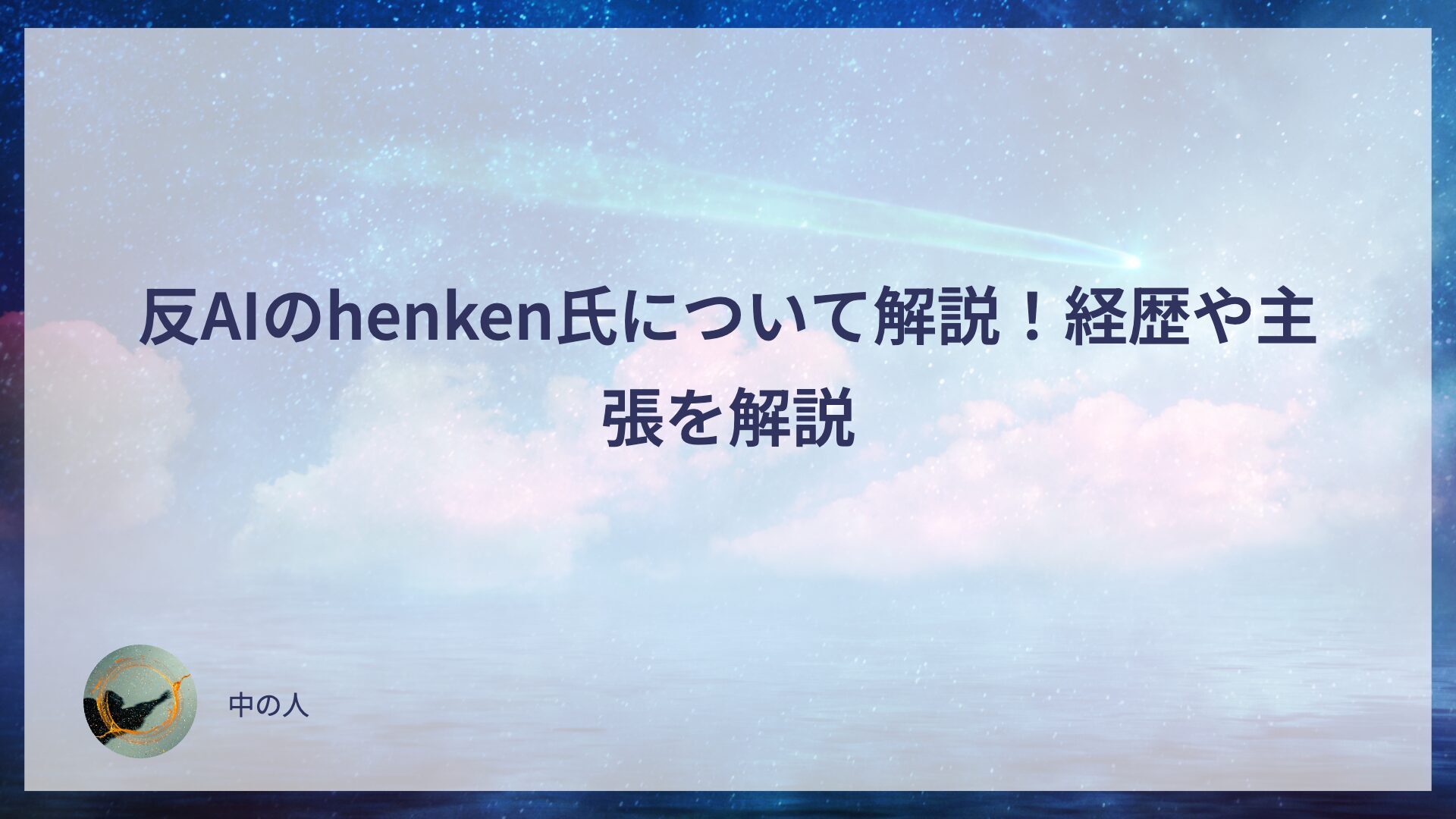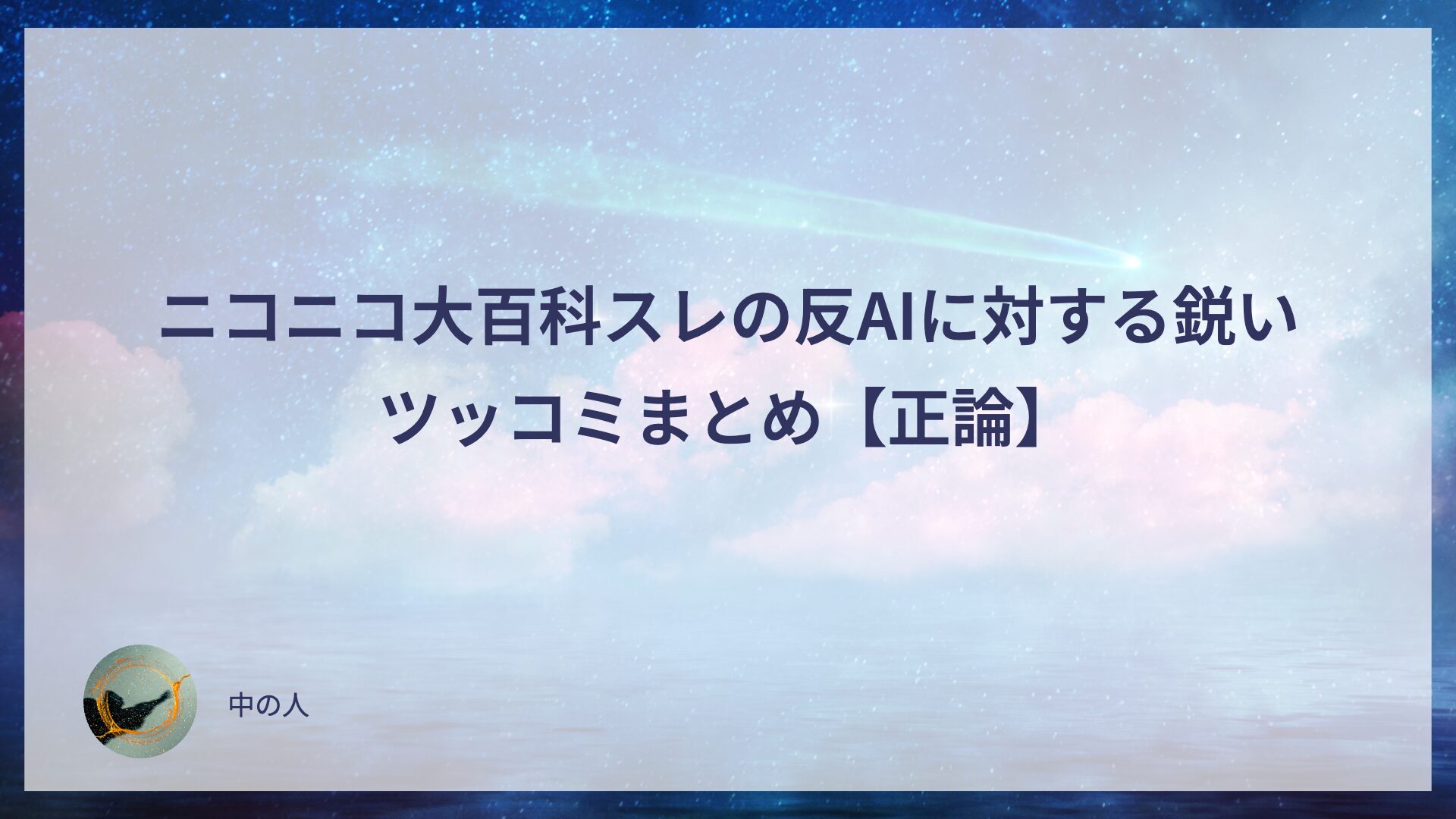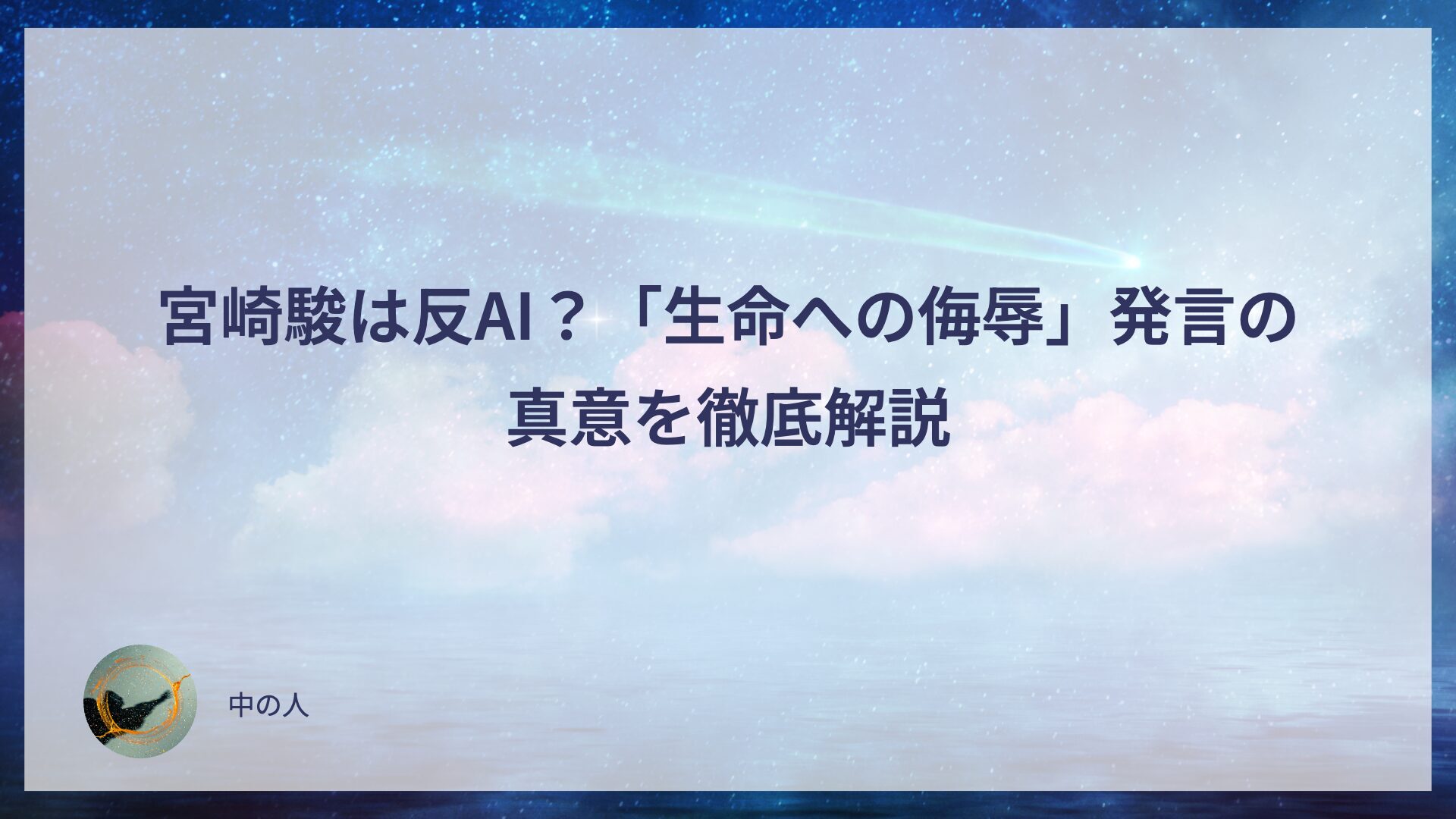反AI絵師の主張と問題点|AIとの共存が必須の時代へ
「反AI絵師」という言葉を目にする機会が増え、なぜAIに強く反対するのか、その主張や背景が気になっていませんか?この記事では反AI絵師が生まれる理由から、運動の中心人物や関連するトラブルまでを解説します。
最後まで読めば生成AIを巡る対立の構造が明確になり、これからのクリエイターに求められる視点が手に入ります。

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
絵師が反AIを主張する理由

絵師が反AIを主張する理由として以下の内容を解説します。
- 著作権と「無断学習」の問題
- クリエイターの仕事が奪われる
- 感情論と技術への誤解
- 炎上したAIサービスの事例
著作権と「無断学習」の問題
絵師が反AIを主張する最も大きな理由は、著作権に関する懸念です。多くの生成AIはインターネット上に存在する膨大な画像を学習データとして利用しており、その中にはクリエイターが著作権を持つイラストも含まれています。
反AIの人々は「自分の作品を無断でAIに学習させられた」「絵柄を盗まれた」と捉え、著作権侵害であると強く主張します。自身の努力の結晶である作品がテクノロジーのために利用されることに対して、強い不満や抵抗感を持っているのです。
しかし、日本の現行著作権法では、第30条の4において「情報解析」を目的とする場合、著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。つまり、AIの学習は法的には違法とは言えないグレーゾーンなのが現状です。
» 文化庁「著作権テキスト」(外部サイト)
とはいえ、法的に問題がないとしても、自分の作風に酷似したイラストがAIによって簡単に生成されてしまう状況は、多くの作り手にとって受け入れがたいものです。
文化庁もこの問題を認識しており、AIと著作権に関する議論やガイドラインの策定を進めていますが、明確な結論には至っていません。
クリエイターの仕事が奪われる

生成AI技術の急速な進化は、クリエイターの仕事に対する深刻な不安を引き起こしています。ソーシャルゲームのキャラクターイラストや、Webサイトの挿絵、広告用のイメージ画像といった分野では、AIによる代替が進むのではないかと危惧されているのです。
AIは人間では考えられないほどのスピードで、一定水準以上の品質を持つイラストを大量に生成できます。これまでイラストレーターに発注されていた仕事が減少し、生計を立てられなくなるクリエイターが増えるのではないか、という懸念が広がっています。
デジタル環境のみで制作活動を行ってきたクリエイターは、自身の制作物とAI生成物の境界が曖昧になることに強い危機感を抱いています。AIもデジタルデータとしてイラストを出力するため、発注者側が「AIで十分」と判断しやすくなる状況が生まれているからです。
AIはあくまで過去のデータを元に生成するツールであり、全く新しい概念や独創的な世界観を生み出すことはできません。AIには真似できない企画力やより高度な創造性がクリエイターに求められるようになります。
感情論と技術への誤解
多くのクリエイターは、長年の努力と情熱を注いで独自の画風や技術を磨いてきました。創作プロセスそのものに価値があると考えており、AIがその過程を省略して結果だけを模倣することに、強い嫌悪感や憤りを抱いています。
現在の生成AIは特定の画像をコピーして貼り付ける「盗用」とは異なり、学習したデータの特徴を数学的に解析し、新しい画像を再構成する仕組みです。この技術的な違いから、AIを単純に泥棒と呼ぶことはできないのです。
一部の反AI派は「Glaze」や「Nightshade」といった、AIによる学習を阻害するツールを利用しています。作品にノイズを加えてAIの学習を困難にするものですが、その効果は限定的であり、万能ではありません。
炎上したAIサービスの事例

クリエイターの反AI感情を決定的にした事件の一つに、2022年8月に公開された「mimic(ミミック)」というAIサービスを巡る騒動があります。
mimicは特定のイラストレーターの画風をAIに学習させ、その絵柄に似たイラストを生成できるというサービスでした。
開発元はクリエイターの創作活動を支援する目的で提供しましたが、これが「絵柄を盗むツールだ」として、公開直後からSNS上で猛烈な批判を浴びたのです。
多くの絵師たちが「自分の絵柄が他人に勝手に使われてしまう」「努力して築いた個性が簡単にコピーされる」と強く反発し、大規模な抗議運動に発展しました。結果としてmimicは公開からわずか1日でサービスを一時停止せざるを得なくなりました。
この一件はクリエイターコミュニティにAIへの強い不信感を植え付け、組織的な反AI運動が本格化する大きなきっかけになったと言えるでしょう。
反AI運動の中心人物と関連する騒動

ここからは反AI運動の中心人物と関連する騒動について以下の内容を解説します。
- 運動を主導した中心人物
- 発端となったmimic騒動
- 殺害予告に発展したLoRA問題
- AI利用を疑われた絵師たち
運動を主導した中心人物
イラストレーターの木目百ニ氏やhenken氏らは、早い段階からAIによる無断学習の問題を強く批判し、多くのクリエイターの支持を集めました。
彼らは「#NOMORE無断生成AI」といったハッシュタグを作成し、SNS上でAIに反対する意思表示を行うキャンペーンを展開しました。このハッシュタグは多くのクリエイターに共感を呼び、プロフィールや投稿に掲げることで、反AIの立場を明確にするムーブメントへと発展していきました。
彼らの発信はAIへの不安を抱えていたクリエイターたちを結びつけ、大きな声として社会に届ける役割を果たしました。一方で、その主張の強さから、AIを利用するクリエイターや技術開発者との間に対立構造を生み出す一因となった側面もあります。
発端となったmimic騒動
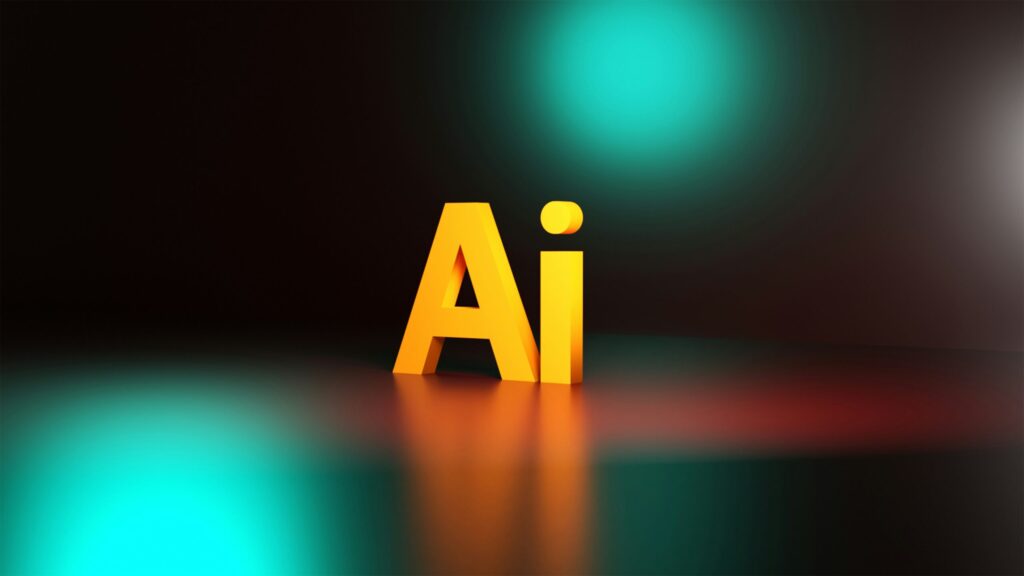
記事内で一度解説しましたが、2022年8月のmimic騒動は、反AI運動が組織化する直接的なきっかけとなりました。mimicの登場はクリエイターが作り上げた絵柄が、テクノロジーによって簡単に複製・利用されるという現実を突きつけました。
この騒動で注目すべき点は、サービスの意図とユーザーの受け止め方の間に、致命的なすれ違いがあったことです。
開発側はあくまで「自分の絵柄でイラストを生成するためのツール」として提供しましたが、クリエイター側は「第三者が他人の絵柄を盗むためのツール」と解釈しました。
この認識のズレが、クリエイターたちの「自分たちの創作文化が破壊される」という強い危機感に火をつけました。mimicはサービス停止に追い込まれましたが、この一件を通じてクリエイターたちは団結し、AI技術に対して明確な「NO」を突きつける大きな力となったのです。
殺害予告に発展したLoRA問題
AIを巡る対立は、深刻な犯罪行為にまでエスカレートすることがあります。その象徴的な事件が、人気イラストレーター「裏方」氏を巡る一連の騒動です。
2024年1月、裏方氏の画風を無断で学習させたAIモデル(LoRA)が、海外の投稿サイトで公開されました。
本人がモデルの削除を求めて抗議したところ、これに反発した一部のユーザーから「創作活動の邪魔をするな」といった誹謗中傷が殺到し、ついには殺害予告まで送り付けられるという異常事態に発展しました。
この事件は、AIによる権利侵害がクリエイターの生命の安全さえも脅かす危険性を示したものであり、社会に大きな衝撃を与えました。裏方氏は法廷闘争の末に勝訴しましたが、精神的に大きなダメージを負ったとされています。
AI利用を疑われた絵師たち

反AI感情の高まりは、AIを全く利用していないクリエイターにまで被害を及ぼす「魔女狩り」のような状況を生み出しています。著名なイラストレーターである、あらいずみるい氏がその一例です。
2023年8月、あらいずみ氏がコミックマーケットで発表した手描きの新作イラストに対し、SNS上で「これはAIで生成したのではないか」という根拠のない疑惑が投げかけられました。
疑惑は瞬く間に拡散され、あらいずみ氏は制作途中のラフ画像などを公開し、手描きであることを自ら証明せざるを得ない状況に追い込まれました。
このような事態はAI生成物への不信感が極度に高まった結果、少しでも画風に違和感があるとすぐにAIだと決めつけて攻撃する、という風潮が生まれていることを示しています。
クリエイターは、自身の作品がAI生成だと疑われないように、常に証明の準備をしておかなければならないという、異常なプレッシャーに晒されています。健全な創作活動を著しく阻害するものであり、反AI運動がもたらした負の側面と言えます。
反AI絵師の主張の矛盾点・ダブルスタンダード

反AIを掲げる人々の主張を深く見ていくと、いくつかの矛盾点やダブルスタンダード(二重基準)が存在するという指摘があります。ここでは代表的な論点を3つ取り上げます。
- 二次創作とAI学習の矛盾点
- 「人の学習」は許されるという論理
- SNS規約と学習拒否の矛盾
二次創作とAI学習の矛盾点
反AIの主張には、二次創作文化における矛盾点が存在します。AIによる「無断学習」を著作権侵害の観点から強く批判する一方で、二次創作もまた、原作の著作権者の許諾を得ずにキャラクターや世界観を利用して創作を行う側面を持つからです。
多くのクリエイターがファンアートを創作文化として楽しみ、自身の技術向上やファンとの交流のために作品を発表しています。この文化が多くの人々に愛され、コンテンツ業界の発展に貢献してきたことは事実です。
しかし、他者の創造物から影響を受けて新たな作品を生み出すという構造は、生成AIのプロセスと共通する部分があります。二次創作は文化として容認し、AIによる学習や生成は「盗用」や「搾取」と断じる姿勢は矛盾していると捉えられても仕方がありません。
「人の学習」は許されるという論理
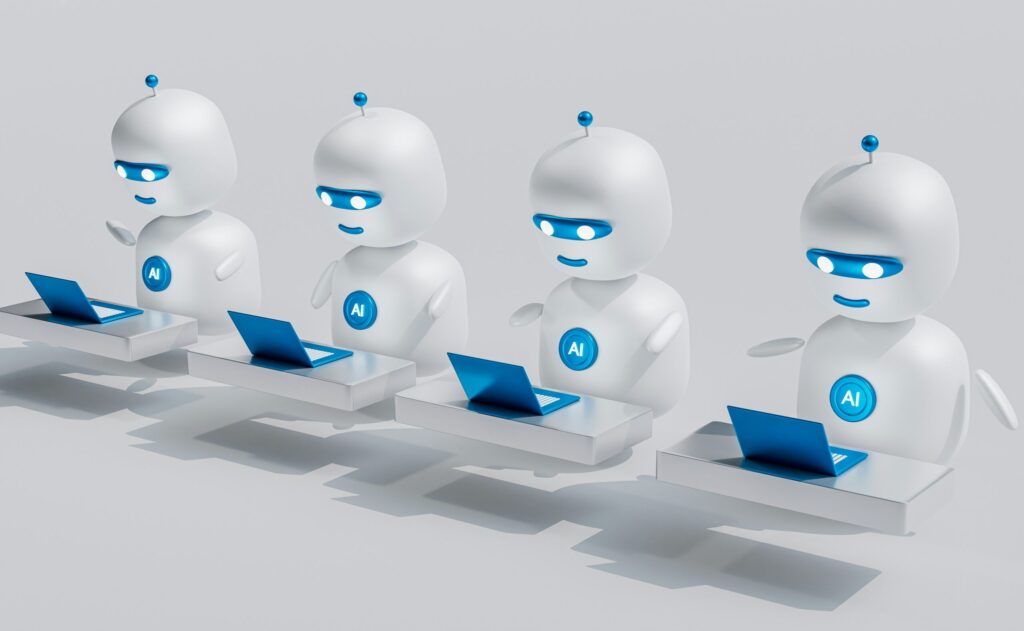
人間のクリエイターが他者の作品から影響を受けることと、AIがデータを学習すること同じことではないかといった指摘もあります。クリエイターが独自の画風を確立する過程では、尊敬する作家の作品を模写したり、様々な表現技法を参考にしたりすることが不可欠です。
この「見る」「真似る」といった人間の学習プロセスも、広い意味では一種の無許諾の学習と捉えることができます。インターネットで画像検索をしながら作品を描く行為は、多くのクリエイターにとって日常的な光景です。
反AI派は人間の学習を「本質を学ぶ創造的な行為」、AIの学習を「データを統計的に再構成する機械的な行為」と区別しようとします。とはいえ、外部の情報を取り入れて自身の表現に活かすという根本的なプロセスにおいて、両者を明確に分ける客観的な基準は曖昧です。
SNS規約と学習拒否の矛盾
X(旧Twitter)をはじめとする主要なSNSプラットフォームは、利用規約の中でユーザーが投稿したコンテンツをAIの学習を含むサービス改善のために利用する権利を持つことを明記しているのが一般的です。
ユーザーはアカウントを作成し、サービスを利用する時点でこの規約に同意しています。プラットフォームが提供する高い拡散力といったメリットを享受しながら、規約の一部であるAI学習だけを選択的に拒否するという姿勢が非難されているのです。
2023年9月にはXがプライバシーポリシーを改定し、投稿データをAIのトレーニングに利用する旨をより明確にしました。この事実を知らない、あるいは無視したまま「無断学習反対」と主張し続けることは、自らが同意した契約内容と反する行動を取っていることになります。
AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。
今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。
- 仕事を奪われる
- 格差が広がる
- 思考停止してしまう
仕事が奪われる
「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。
- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ
- 俺は現場に出て働いているから関係ない
- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?
こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。
近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。
その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。
つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。
そうなってからやる気を出してももう遅いのです。
情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。
AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。
AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。
AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。
AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。
問題は「自分はどちら側に立つか」です。
思考停止してしまう
AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。
AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。
普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。
AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。
つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。
大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。
AIとの共存か、時代に取り残されるか

クリエイターがこの先も第一線で活躍し続けるために、どのような視点やスキルが求められるのでしょうか。ここでは以下の内容を解説します。
- AIはクリエイターの敵ではない
- 独自のブランドを形成する
- 規制ではなくルール整備の動き
- これから求められるスキルとは
AIはクリエイターの敵ではない
生成AIを一方的に「敵」と見なすのではなく、創作活動を助ける強力な「道具」として捉え直す視点が重要です。AIはクリエイターの仕事を全て奪う存在ではありません。むしろ、使い方次第で人間の創造性を拡張し、新しい表現を生み出す可能性を秘めています。
実際に、プロの現場でもAIの活用は始まっています。例えば、物語のアイデア出しやキャラクターデザインの初期案作成、背景イラストの補助など、制作プロセスの一部をAIに任せることで、作業時間を大幅に短縮できます。
これにより、クリエイターはより本質的な、創造性の高い部分に集中できるようになるのです。
AIによって生成されたイラストが市場に溢れたとしても、人間が心を込めて描いた手描きの作品や、独自のストーリーを持つ作品の価値が失われるわけではありません。むしろ、AI生成物との違いが明確になることで、人間のクリエイターならではの価値が再認識される可能性もあります。
AIを恐れて拒絶するのではなく、いかにして自分の創作に活かすかを考える姿勢が、これからのクリエイターには求められます。
独自のブランドを形成する

AI時代にクリエイターが活躍し続けるには「あなただからお願いしたい」と言われる強力な独自ブランドの形成が不可欠です。生成AIは特定の画風を模倣できても、作家自身の個性や作品に込めた世界観、クライアントとの信頼関係といった、属人的な価値までは再現できないからです。
独創的な世界観を持つ作家には、その世界の一部を求めて依頼が来ます。丁寧なコミュニケーションや確実な納期管理といったプロとしての姿勢も、AIにはない人間ならではの価値であり、強力なブランドの一部となります。
単なる「絵を描ける人」から脱却し、作品や活動全体でファンを魅了する、唯一無二の「クリエイターブランド」を確立しなくてはなりません。それがAIでは代替不可能な存在になるための鍵です。
規制ではなくルール整備の動き
生成AIを巡る様々な問題に対し、社会は「全面的な禁止」ではなく、「健全な利用のためのルール作り」という方向で動き出しています。議論の焦点となっているのは、主に以下の二点です。
- 学習データの透明化
- 生成物の権利の明確化
学習データの透明化
AIが何を学習したのかを明確にする「データセットのクリーン化」が求められています。著作権を侵害しない、あるいは権利者から許諾を得たデータのみで学習したAIであれば、クリエイターも安心して利用できます。
生成物の権利の明確化
AIが生成したイラストの著作権は誰に帰属するのか、商業利用はどこまで許されるのか、といったルールを明確にすることが重要です。明確なルールがあれば、クリエイターは安心してAIをツールとして利用でき、発注者側もトラブルを恐れずにAI生成物を活用できます。
これから求められるスキルとは

AIが普及する時代において、クリエイターには以下のスキルが求められます。
- 「プロンプトエンジニアリング」の能力
- 「企画力」と「構想力」
- 「コミュニケーション能力」や「ディレクション能力」
「プロンプトエンジニアリング」の能力
AIを効果的に使いこなす技術、すなわち「プロンプトエンジニアリング」の能力です。自分の意図を的確に言語化し、AIに指示を与えるスキルは、これからのクリエイターにとって必須の教養となります。
「企画力」と「構想力」
AIは既存のデータの組み合わせでしかありません。誰も見たことのないような新しいコンセプトをゼロから生み出す力は、人間のクリエイターが価値を発揮する最大の領域です。
「コミュニケーション能力」や「ディレクション能力」
AIは単なる道具であり、最終的な作品の質を決めるのは、それを扱う人間の感性と判断力に他なりません。これらの人間的なスキルを磨き続けることが、AI時代を生き抜く鍵となります。
まとめ
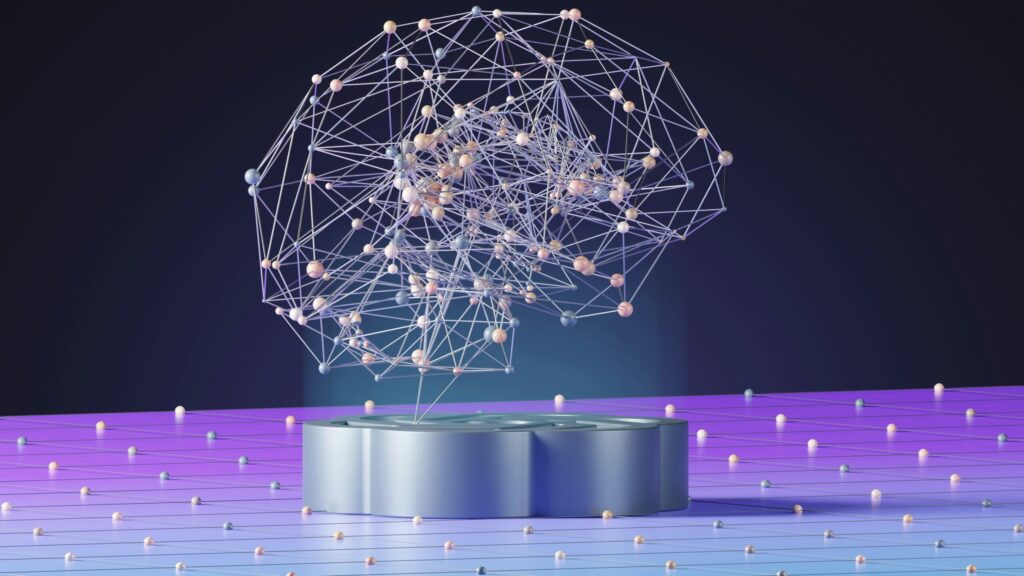
この記事では反AIを主張する絵師の背景から、運動が引き起こしたトラブル、そして私たちが向き合うべき未来について解説しました。生成AIは、クリエイターにとって脅威であると同時に、大きな可能性を秘めたツールです。
技術を正しく理解し、社会全体で建設的なルールを築いていく姿勢が、今まさに求められています。