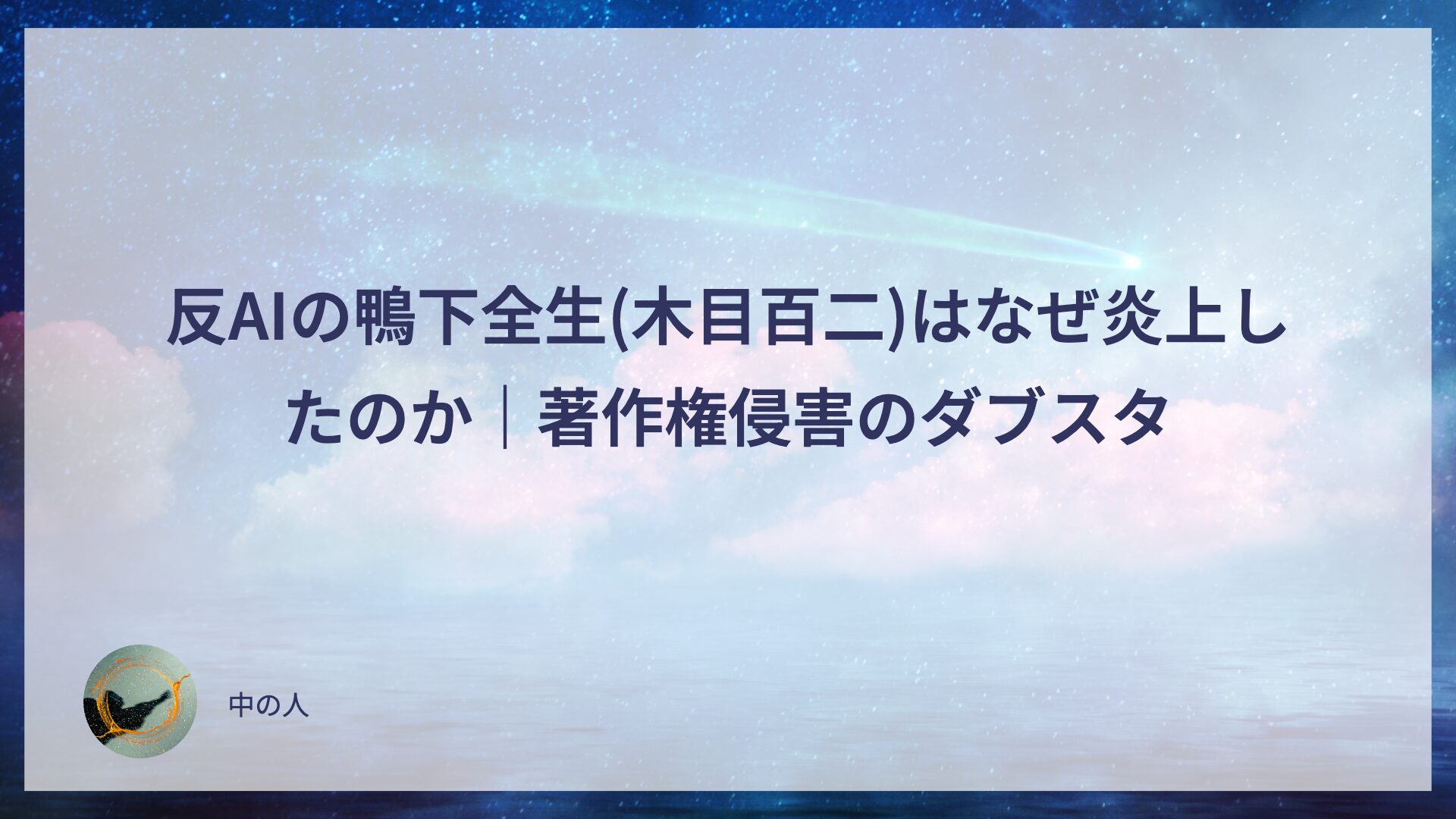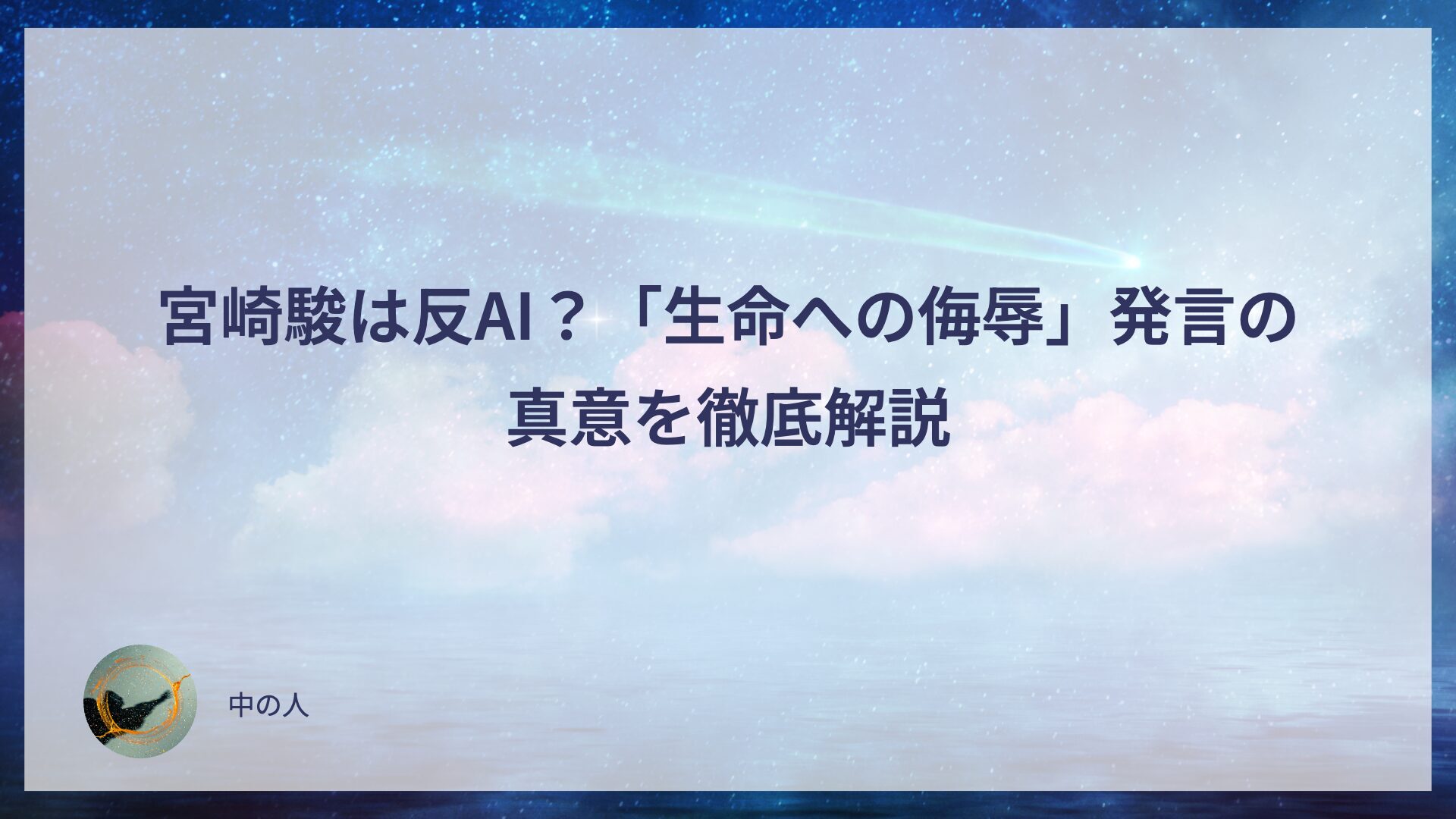芝石ひらめ氏が反AI派から攻撃?炎上と二次被害を解説
この記事では、芝石ひらめさんがAI使用疑惑をかけられた経緯から、LoRAという技術による深刻な二次被害までを網羅的に解説します。

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
人気絵師芝石ひらめを襲った反AIからの疑惑
- 発端は突然のAI使用疑惑
- 疑惑を否定するも炎上へ
- 激しい追及に疲れ果て休止
発端は突然のAI使用疑惑
人気イラストレーターである芝石ひらめさんへの騒動は、一部のユーザーからAIイラストの使用疑惑をかけられたことから始まりました。フォロワー76万人を抱える芝石ひらめさんは、これまでAI技術に対して特に言及することなく、沈黙を保っていました。
しかし、自身の作品に対して何の前触れもなく「AIを使っているのではないか」という指摘が寄せられます。
クリエイターが新しい表現や塗り方を試みた際に、それが見慣れないものであるためにAI生成物と誤解されるケースは、他のイラストレーターの事例でも見受けられます。
この突然の疑惑が、一連の炎上騒動の引き金となりました。
疑惑を否定するも炎上へ
突然の疑惑に対し、芝石ひらめさんは自身のX(旧Twitter)アカウントで明確に否定しました。芝石ひらめさんはAIに対しては不快感を抱いており、今後も使う気はないという趣旨の投稿を行い、自身の潔白を主張します。
ところが、否定投稿が一部の反AI派と見られるユーザーによって、意図しない形で解釈されます。言葉の細部を捉えて揚げ足を取ったり、否定の仕方が不十分であると主張したりする声が上がり始めました。
これに野次馬も加わる形で、かえってAI使用疑惑が拡散されるという皮肉な結果を招きます。
激しい追及に疲れ果て休止
芝石ひらめさんのアカウントには、AI使用を決めつけるようなリプライや引用が執拗に送られ続けます。中には、制作過程のタイムラプス映像やレイヤーデータの公開を要求するといった、証明を強要するような動きも見られました。
芝石ひらめさんは一連の騒動に対して疲れ果ててしまった様子でした。最終的に、SNSでの新たな投稿は途絶え、事実上の活動休止状態に陥ってしまいます。創作活動に専念すべきクリエイターが、根拠の薄い疑惑によって活動の継続が困難になるという、非常に悲しい結末を迎えました。
無断学習LoRAによる二次被害と終わらない嫌がらせ
- LoRAモデルの無断作成
- 規約違反コンテンツの生成
- 深刻化する風評被害
LoRAモデルの無断作成
AI使用疑惑の炎上が沈静化しない中、事態はさらに深刻な局面を迎えます。第三者によって、芝石ひらめさんの公開作品が無断で学習され、特定の絵柄を再現するための追加学習ファイル「LoRA(Low-Rank Adaptation)」が作成されてしまったのです。
LoRAとは、元のAIモデル全体を再学習するのではなく、少数のパラメータを追加で学習させることで、特定のキャラクターや画風を効率的に模倣する技術です。
計算コストが低く手軽に作成できる利点がある一方で、クリエイターの絵柄を本人の許可なく「複製」する目的で悪用されるケースが後を絶ちません。芝石ひらめさんのケースでは、本人への嫌がらせを目的として利用されました。
規約違反コンテンツの生成
無断で作成された芝石ひらめさんの絵柄LoRAは極めて悪質な形で使用されました。このLoRAを用いて、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の二次創作イラストが生成され、SNS上に投稿されたのです。
ウマ娘プロジェクトは、実在の競走馬をモチーフにしているという特性上、二次創作に関して詳細なガイドラインを設けています。特に、キャラクターのイメージを著しく損なう性的描写や暴力的な表現は明確に禁止されています。
今回生成された画像は、このガイドラインに違反する内容を含んでいました。つまり、加害者は芝石ひらめさんの絵柄を無断で利用した上で、特定のコンテンツホルダーが定める規約を意図的に破るという二重の加害行為を行ったことになります。
深刻化する風評被害
芝石ひらめさん本人は一切関与していないにもかかわらず、その特徴的な絵柄で規約違反のイラストが公開されることで、事情を知らない第三者からは「芝石ひらめさんが規約違反のイラストを描いた」と誤解されかねません。
同様の被害は他のイラストレーターにも及んでいます。LoRAの悪用は、クリエイター本人に「描いていない罪」を着せるという、極めて悪質な情報汚染を引き起こす問題といえます。
疑惑が示すクリエイターを取り巻くAI問題の本質

- これは現代の魔女狩りか
- X(旧Twitter)での世間の反応
- クリエイターの自衛策とは
これは現代の魔女狩りか
芝石ひらめさんの事例は氷山の一角であり、多くのクリエイターが同様の被害に苦しんでいます。「スレイヤーズ」で知られるベテランイラストレーターのあらいずみるいさんが、普段と違う塗り方を試した同人誌の表紙を「AI堕ちした」と非難されました。
あらいずみるいさんは、制作過程のレイヤーデータを公開することで潔白を証明しました。
また、無名のイラストレーターが「AIにしか見えない」「タイムラプスを出せ」と執拗に証明を強要されるケースも散見されます。これらの行為は対象者を一方的に断罪しようとする点で、まさに「現代の魔女狩り」と呼ぶべき状況です。
クリエイターが新しい表現に挑戦する自由を奪い、萎縮させる深刻な問題となっています。
» 反AIの魔女狩りはなぜ起こる?背景にある嫉妬と暴走の心理
X(旧Twitter)での世間の反応
芝石ひらめさんの一件に関して、X(旧Twitter)上では様々な意見が交わされました。大多数のユーザーは芝石ひらめさんに同情し、根拠なく疑惑をかけたアカウントに対して厳しい批判の声を上げています。
クリエイターへの敬意を欠いたノンデリケートな行為であるという意見が多かった印象です。
一方で、議論は別の方向にも発展しました。疑惑をかけたアカウントが本当に「反AI」なのか、それとも対立を煽るために反AIを装った「AI推進派のなりすまし」ではないか、という憶測も飛び交います。
どちらが真実かは定かではありません。しかし、このような疑心暗鬼が生まれること自体が、AIを巡る議論がいかに複雑化し、不毛な対立構造に陥っているかを示しています。
クリエイターの自衛策とは
このような理不尽な攻撃からクリエイターが身を守るため、技術的な自衛策も開発されています。代表的なツールが、シカゴ大学の研究チームが開発した「Glaze」と「Nightshade」です。
GlazeとNightshadeの仕組み
Glazeは、人間の目には見えにくいノイズを画像に加えることで、AIが絵柄や画風を学習するのを妨害するツールです。
Nightshadeはさらに強力で、画像に「毒」を仕込みます。例えば、犬のイラストにNightshadeを適用すると、AIはそれを「猫」として誤って学習してしまいます。これにより、AIモデル自体を汚染し、無断学習の抑止力となることが期待されています。
各ツールの特徴と注意点
これらのツールはクリエイターにとって心強い味方ですが、万能ではありません。処理に時間がかかる、画像にノイズが入るため画質が多少劣化するといったデメリットが存在します。ネット上では、現状のツールでは絵柄の模倣を完全に防ぐことは難しいという報告もあります。
AIモデル開発側もこれらのツールへの対策を進めており、いたちごっこの状態が続く可能性があります。
まとめ
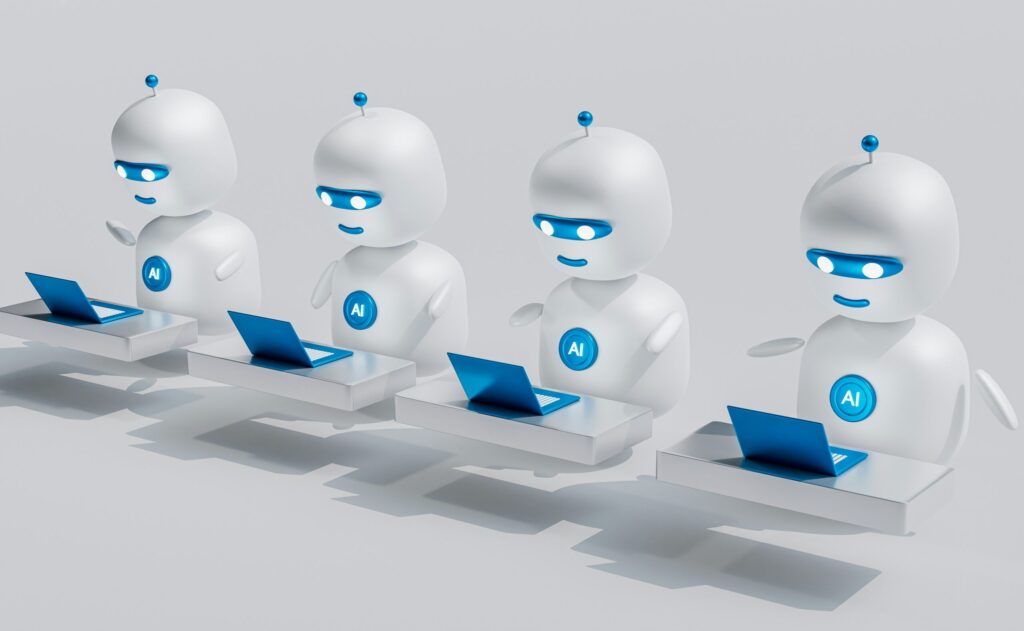
芝石ひらめさんが反AIから受けたAI使用疑惑は、SNS上での根拠なき批判から始まりました。本人が否定した後も騒動は収束せず、無断作成されたLoRAによる二次被害へと発展し、クリエイターの信用を著しく毀損する事態となりました。
この一件は、現代の「魔女狩り」ともいえるAIを巡る過剰な攻撃性と、クリエイターが直面する深刻な権利侵害の問題を浮き彫りにしています。