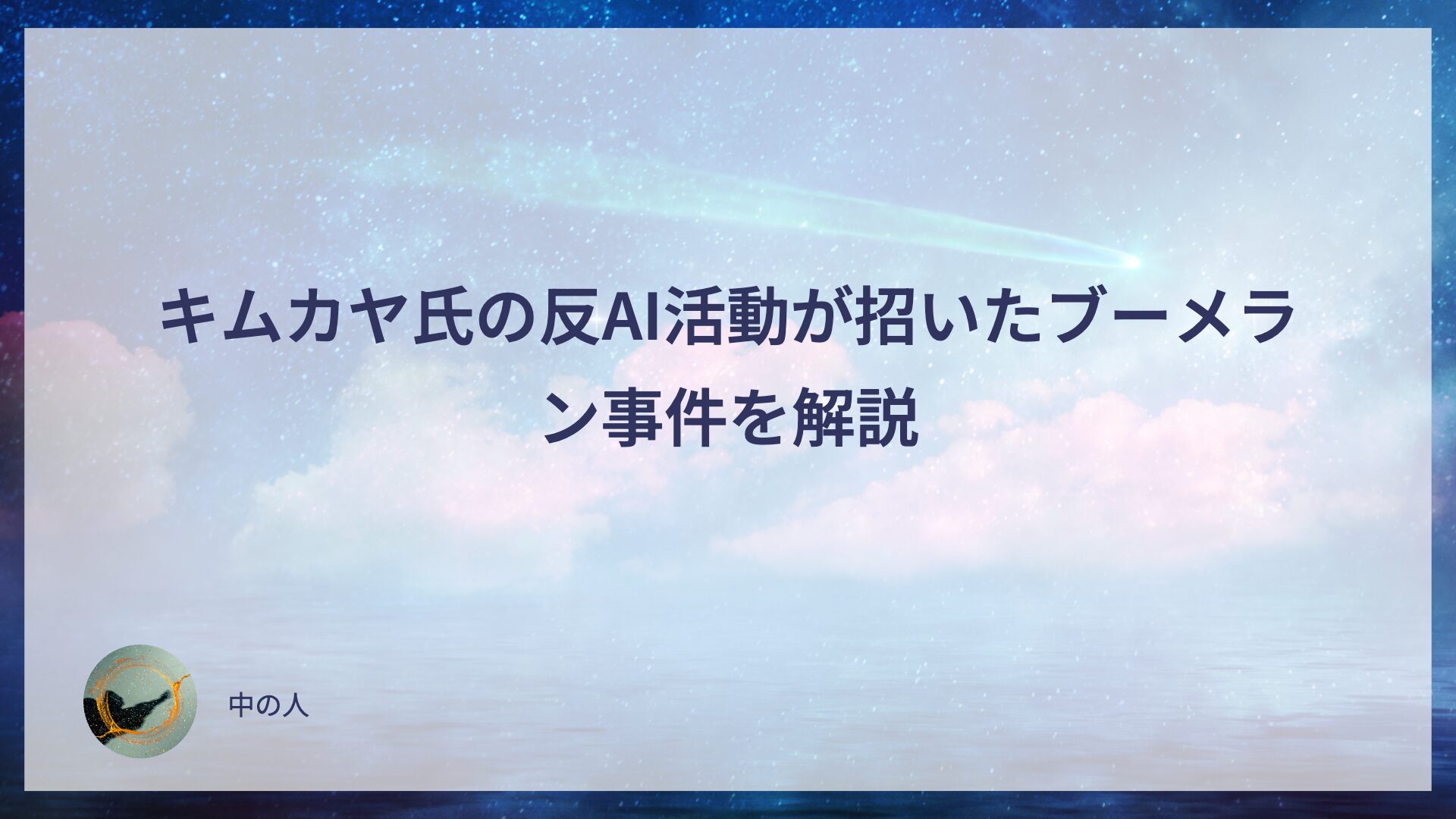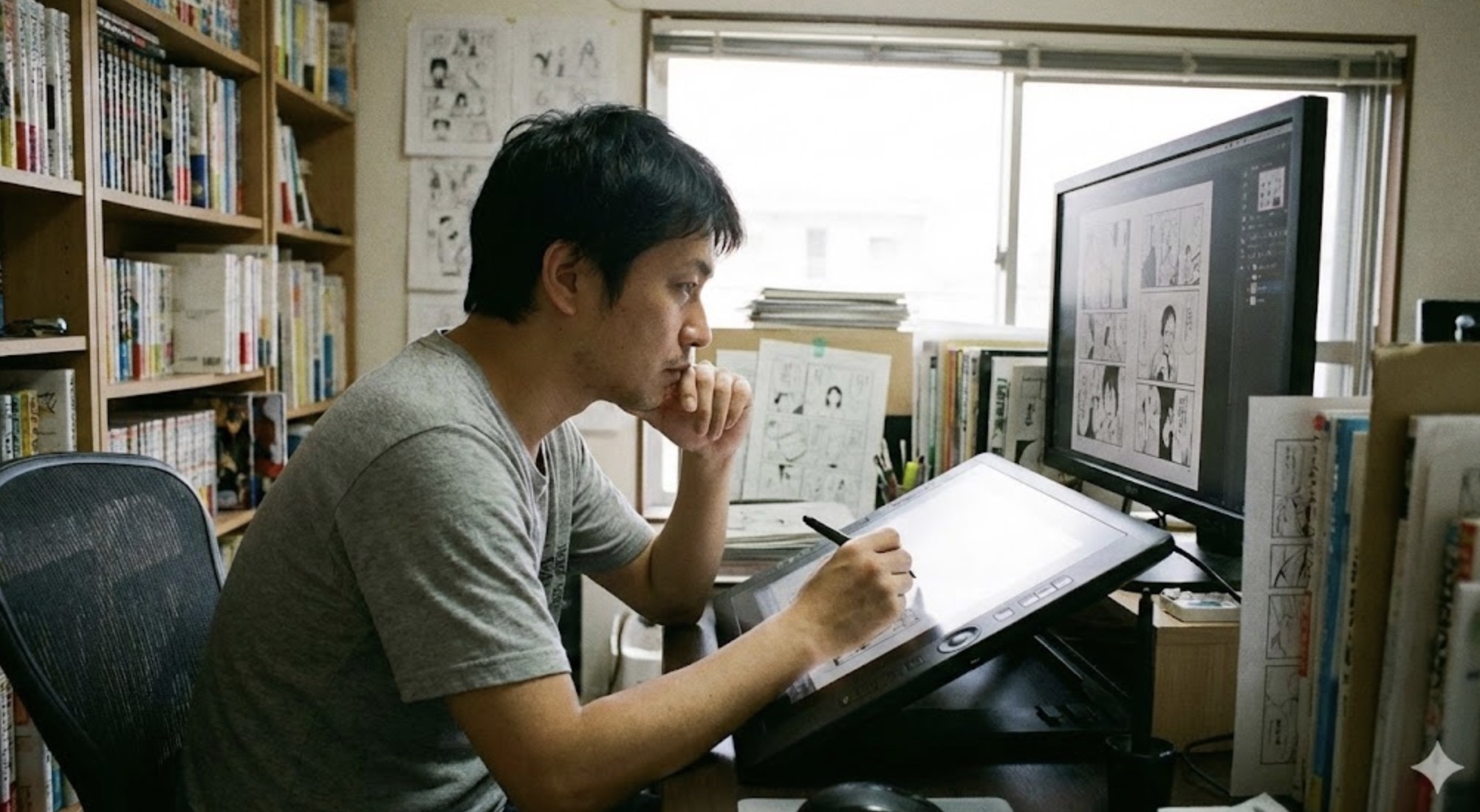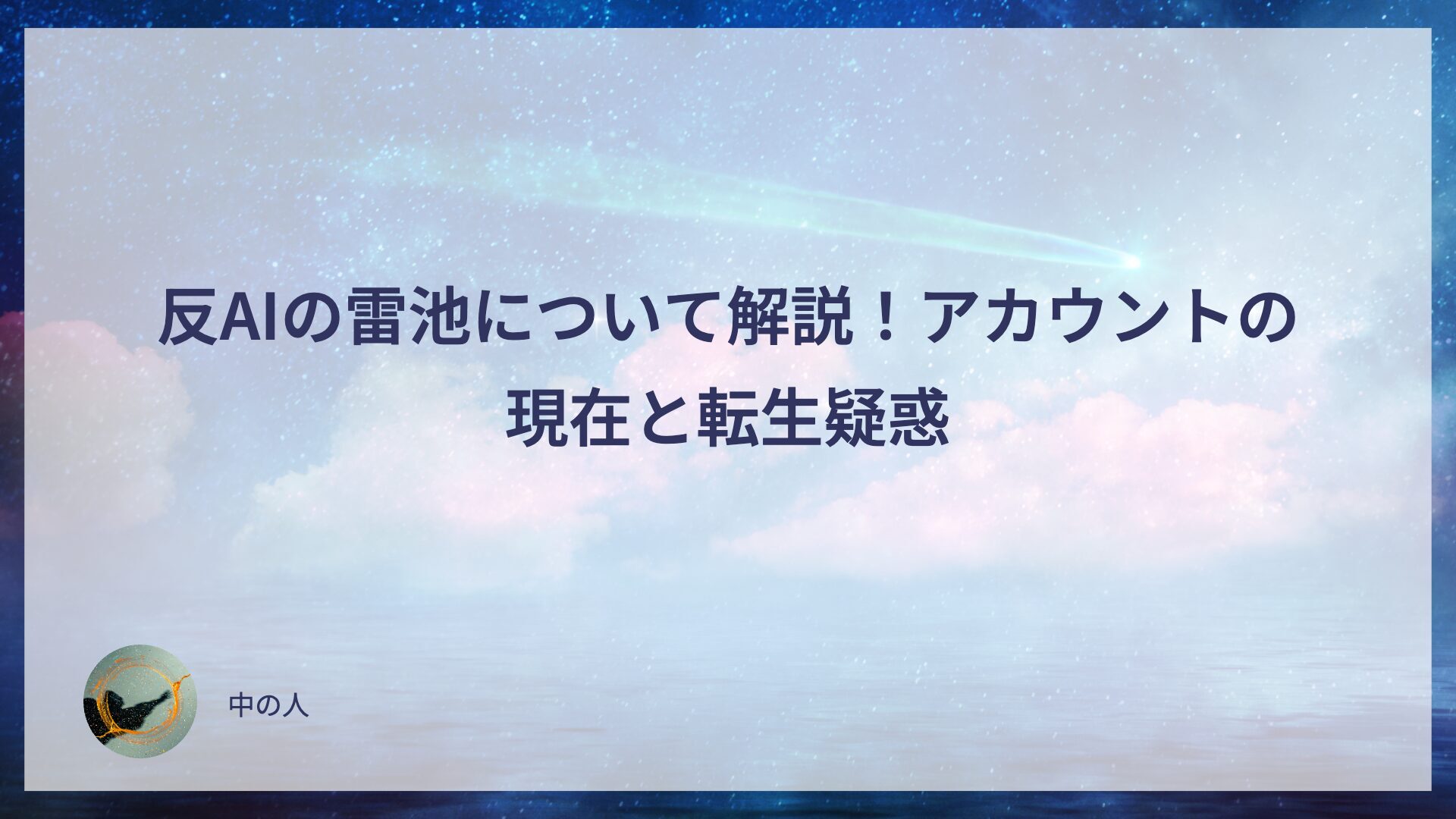反AIが提出したパブコメの結果と要点まとめ|なんjの反応・指摘された問題点も解説
「反AIのパブコメ結果が気になる」「なぜ意見が反映されなかったんだろう」と感じていませんか?この記事では文化庁が示した公式回答と、反AI派の意見が通らなかった背景にある問題点を解説します。
参考ページ
» 「『AIと著作権に関する考え方について(素案)』に関するパブリックコメントの結果について」(外部サイト)

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
そもそも「パブリックコメント」とななにかおさらい
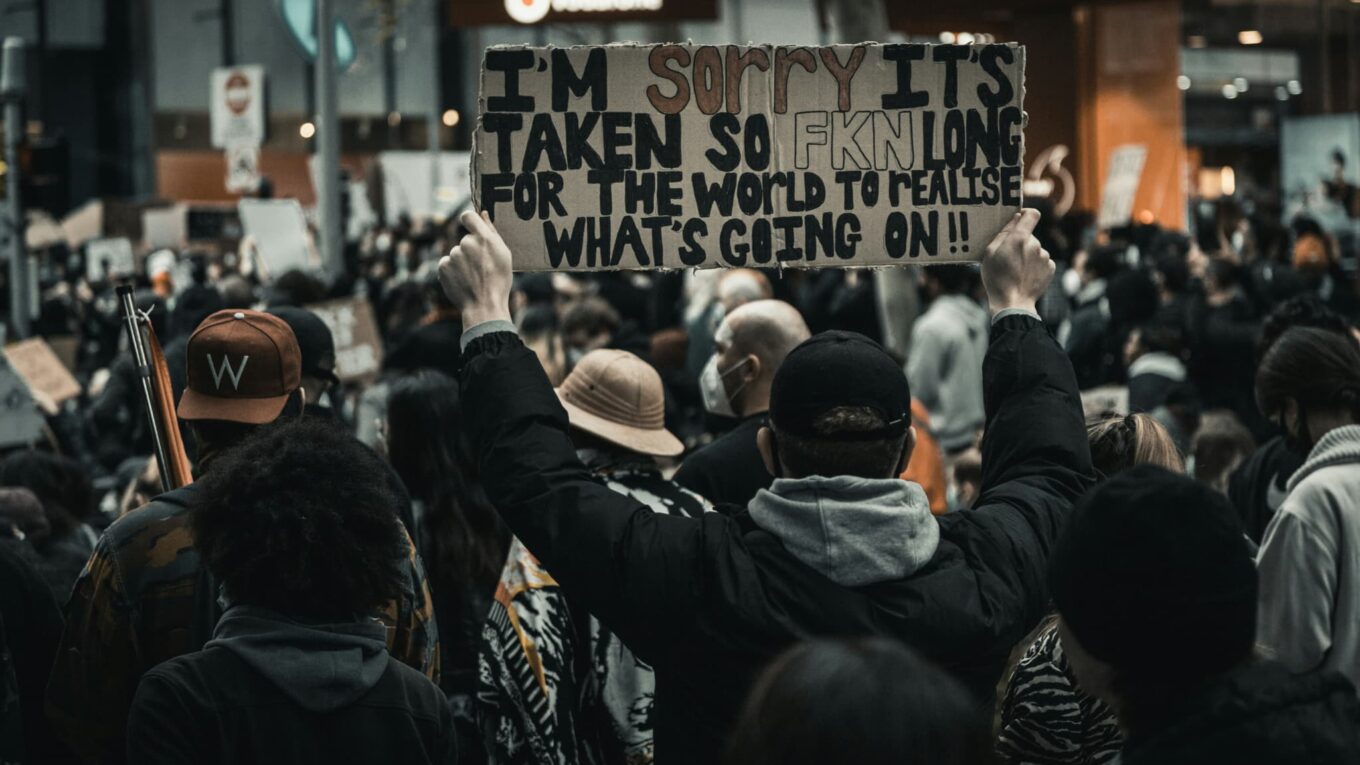
パブリックコメントとは国の行政機関が法律や政令といったルールを新しく作ったり、変更したりする際に、その案を事前に公表して、国民から広く意見を募集する手続きのことです。この制度は行政運営の公正さと透明性を高める目的で導入されました。
パブリックコメントは以下の流れで行われます。
- 案の公表
省庁などの行政機関がこれから定めようとするルールの案(素案)と関連資料を公表します。意見を募集する期間(通常30日以上)も示されます。 - 意見の提出
国民は誰でも公表された案に対して意見を提出できます。意見はオンラインのフォームや電子メール、郵送などの方法で受け付けられます。 - 意見の検討と最終決定
募集期間が終了すると行政機関は寄せられた全ての意見を考慮し、最終的なルールを決定します。 - 結果の公表
最終決定されたルールと共に寄せられた意見の概要と、それに対する行政機関の「考え方」や対応が公表されます。
パブリックコメントが国民投票や多数決とは異なります。意見の数が多ければ採用されるというわけではありません。提出された意見の内容に、どれだけ説得力のある論拠や建設的な提案が含まれているかが重視されます。
反AIのパブコメに対する文化庁の公式回答の要点まとめ

今回のパブリックコメントで文化庁が示したAIと著作権に関する公式な見解を見ていきましょう。主要なポイントは以下のとおりです。
- AIの学習は原則「許諾不要」
- 生成物の侵害判断は従来通り
- アイデアや作風は保護の対象外
- クリエイターへの対価還元を検討
AIの学習は原則「許諾不要」
これは著作権法第30条の4に基づく解釈です。この条文は、著作物を楽しむ「享受」の目的でなければ、情報を解析するために著作物を自由に利用できると定めています。AIがデータを読み込む行為は、この「情報解析」にあたり「享受」ではないと判断されるのです。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
〜中略〜
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
ただし、特定の作品の海賊版と知りながら学習データとして利用する行為などは、開発者側の責任が問われる可能性を高めると注意を促しています。
生成物の侵害判断は従来通り

著作権は既存の作品との「類似性(表現が似ているか)」と「依拠性(元にして作られたか)」の2つの要素で個別に判断されます。
AIを使ったかどうかで判断基準が変わることはなく、あくまで生成されたものが既存の著作物の表現上の特徴を直接感じ取れるかで判断されるのです。
アイデアや作風は保護の対象外
著作権法が保護するのは具体的な「表現」であり、アイデアや作風そのものは保護の対象外である、というのが文化庁の回答です。人の手による模倣でもAIによる生成でも変わりません。
多くのクリエイターが他者の作風から影響を受けて創作活動を行うことと同様に、作風が類似しているだけでは、原則として著作権侵害にはあたらないのです。
とはいえ、特定のクリエイターの市場と競合するような悪質なケースでは、利益を不当に害する場合として権利侵害が認められる余地も残されています。
クリエイターへの対価還元を検討
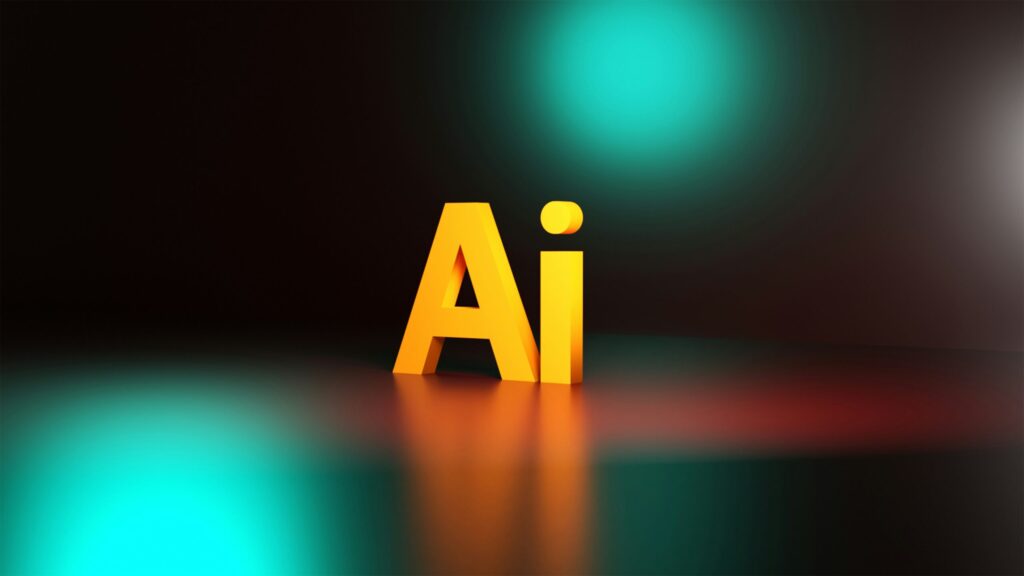
文化庁はクリエイターに対して法律で補償金制度などを設けることは難しいという見解を示しました。AIの学習は原則として適法な行為であるため、対価の支払いを法的に義務付ける根拠がないためです。
しかし、文化庁はクリエイターの創作活動が重要であるとも認識しています。技術的なアプローチや業界の自主的なルール作りを通じて、クリエイターに利益が還元される仕組みを後押ししていく考えを示しています。
なぜ反AIの意見は通らない?指摘された問題点
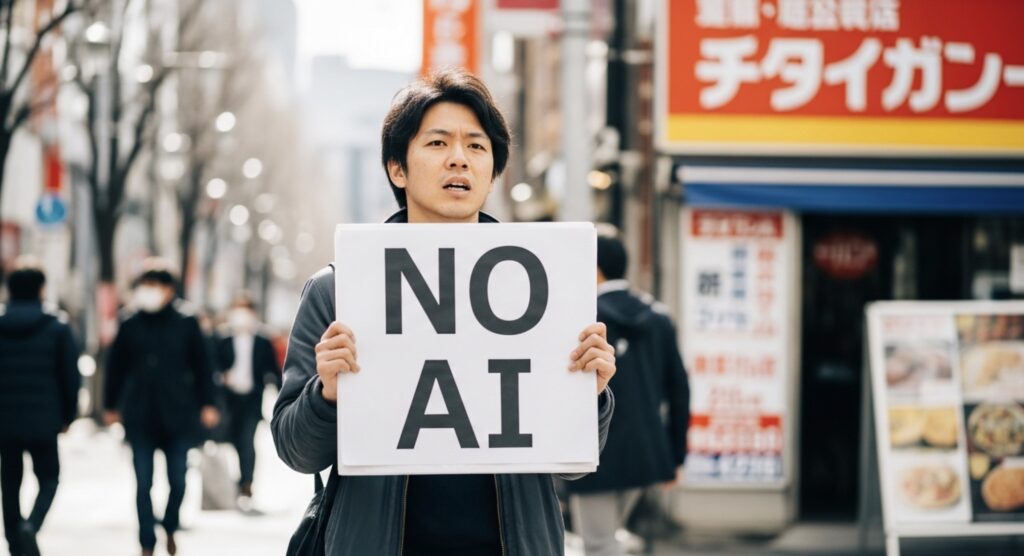
AI(主に画像生成)に対して多くの反対意見が集まったにもかかわらず、結果的にはどの意見も軽く受け流されたような形で終わりました。ここからは反AIの主張が通らなかった理由を考察していきます。
- 感情的な意見が大多数
- 「AIはズルい」という本音
- 既存の法律で対処可能との見解
- 著作権法そのものの誤解
- パブリックコメントを受けたなんjの反応
感情的な意見が大多数
今回寄せられた約2万5千件のパブリックコメントのうち、反対意見の多くは法的な論拠よりも感情的な訴えが中心でした。「クリエイターの努力を無にする」「心がこもっていない」といった意見は、個人の心情としては理解できるものです。
しかし、パブリックコメントは法律の解釈や制度設計に関する意見を求める場です。感情論に終始する意見は、政策判断の材料として採用されにくいという側面があります。
文化庁の回答も個別の被害については「現行法で対応可能」といった内容が多く見られました。これは、感情的な反発と法的な権利侵害は別の問題として切り分けて考えるという姿勢の表れでしょう。
「AIはズルい」という本音

反AI派の主張の根底には著作権侵害への懸念だけでなく「AIは労力をかけずに作品を生み出しており、ズルい」という感情があるのではないかと指摘されています。
長年努力を重ねて技術を習得してきたクリエイターから見れば、簡単な指示で高品質な作品が出力される状況は、不公平に感じられるかもしれません。この感情は、かつてデジタル作画ツールが登場した際のアナログ派の反発にも通じるものがあります。
「二次創作は愛があるから許されるが、AIには愛がないからダメだ」といった主張が見られることも、この感情を裏付けています。しかし、法律は「愛」や「労力」の有無で著作権侵害を判断しません。あくまで客観的な基準に基づいて判断が下されるのです。
既存の法律で対処可能との見解
文化庁はAIによる著作権侵害や嫌がらせといった被害の多くは、既存の法律の枠組みで対処可能であるという見解を示しています。
AIを使って他人の作品そっくりの画像を生成し、自作として公開した場合は著作権侵害として訴えることが可能です。また、特定の個人を誹謗中傷する画像を生成すれば、名誉毀損罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
AIはあくまで道具であり、問題の本質はそれを使う人間の側にあります。AI技術を規制するのではなく、個別の違法行為を取り締まるべきだという考え方です。
著作権法そのものの誤解

反AI派の主張の中には、著作権法を根本的に誤解している意見も多いです。例えば「生成AIは元画像を切り貼りしている(コラージュのようなものだ)」という認識です。
実際のAIは、画像のパターンや特徴を数値データとして学習し、そこから新しい画像を生成する仕組みであり、元の画像をそのまま保存・利用しているわけではありません。
「無断で学習すること自体が違法だ」という主張も多く見られます。これも、著作権法第30条の4で認められた行為であり、法的な誤解にもとづいた意見と言えるでしょう。こうした認識のズレが、議論がかみ合わない一因となっています。
パブリックコメントを受けたなんjの反応
インターネット掲示板のなんでも実況J(なんJ)などでは、パブリックコメントの結果に対して比較的冷静な反応が見られました。目立った意見は以下のとおりです。
- 「まあそうなるだろう」
- 「法律的に考えれば当然の帰結」
- 「お気持ち表明で法律は動かない」
- 「数だけ集めても意味がない」
この反応は、SNSの声と世間一般の認識との間にズレがあることを示唆しています。ネット上の声の大きさが、必ずしも社会全体の総意を反映しているわけではないことが分かります。
AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。
今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。
- 仕事を奪われる
- 格差が広がる
- 思考停止してしまう
仕事が奪われる
「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。
- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ
- 俺は現場に出て働いているから関係ない
- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?
こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。
近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。
その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。
つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。
そうなってからやる気を出してももう遅いのです。
情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。
AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。
AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。
AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。
AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。
問題は「自分はどちら側に立つか」です。
思考停止してしまう
AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。
AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。
普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。
AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。
つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。
大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。
パブコメで意見を届けるために知っておくべきこと
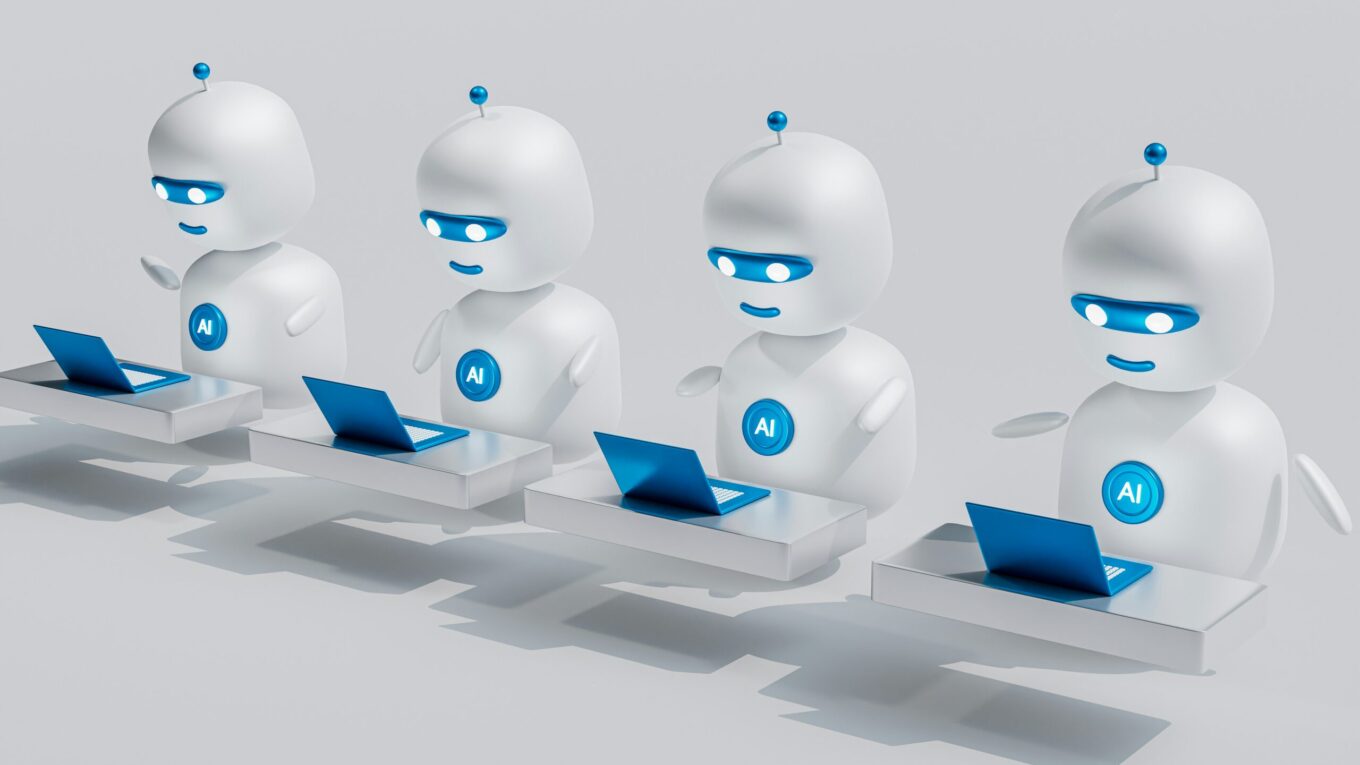
今回のパブリックコメントから学べることは以下のとおりです。
- 「数」より「論理」の重要性
- パブコメは多数決ではない
- 論点がズレた意見は無意味
- 目的と手段のミスマッチ
「数」より「論理」の重要性
パブリックコメントにおいて最も重要なのは意見の数ではなく、その内容の論理性です。今回は約2万5千件の意見が集まりましたが、同じ内容の意見を多数集めても、それが政策に大きな影響を与えるわけではありません。
行政が求めているのは、提示された素案の問題点を具体的に指摘し、より良い制度にするための建設的な対案です。なぜ現行の解釈が問題なのか、法的にどのような矛盾が生じるのか、といった点を論理的に説明することが大切なのです。
パブコメは多数決ではない

パブリックコメントは、国民投票や人気投票のような多数決で物事を決める制度ではありません。たとえ少数意見であっても論理的で説得力のあるものであれば、素案が大きく見直されることもあり得ます。
いくら多くの人が賛成・反対を表明しても、その意見に合理的な根拠がなければ採用されることはありません。「数が多ければ意見が通るはずだ」という考えは、パブリックコメント制度の本質を理解していないと言えるでしょう。
論点がズレた意見は無意味
提出する意見は、募集されている議題の範囲内に収まっている必要があります。
今回の議題は「AIと著作権に関する考え方」でした。ところが、寄せられた意見の中には「AIによって仕事を奪われる」「AI生成物は不快だ」といった、著作権法の解釈とは直接関係のない内容も多く含まれていました。
文化庁の所管する著作権法の議論から外れているため「今回の議題とは関係ありません」として扱われてしまいます。意見を提出する際は、どの法律や制度に関する議論なのかを正確に把握することが重要です。
目的と手段のミスマッチ

今回のパブリックコメントに対して反AI一部では「様式は気にせず、とにかく意見を送ろう」という呼びかけも見られました。気持ちを伝えることは大切ですが、行政手続きにおいては定められたルールに従うことが前提となります。
論点が不明確であったり議題と無関係な内容であったりする意見は、せっかく提出しても検討の対象になりません。
自分の主張を政策に反映させたいのであれば、感情的な訴えではなく問題点を整理し、冷静かつ論理的な文章で意見をまとめる姿勢が重要です。
まとめ

文化庁のパブコメ結果ではAIの学習は著作権法上、原則容認されるという公式見解が示されました。反対意見の多くは感情論や法解釈の誤解が中心で、採用には至りませんでした。
この一件は、パブリックコメントが数ではなく論理性を重視する手続きであり、法的な議論の重要性を示しています。
- 文化庁はAI開発の学習利用を基本的に容認
- 反AI派の意見は感情論と法解釈の誤解が中心
- パブコメは数よりも論理的な内容が求められる
- 法的な議論と個人の感情は分けて考えるべき