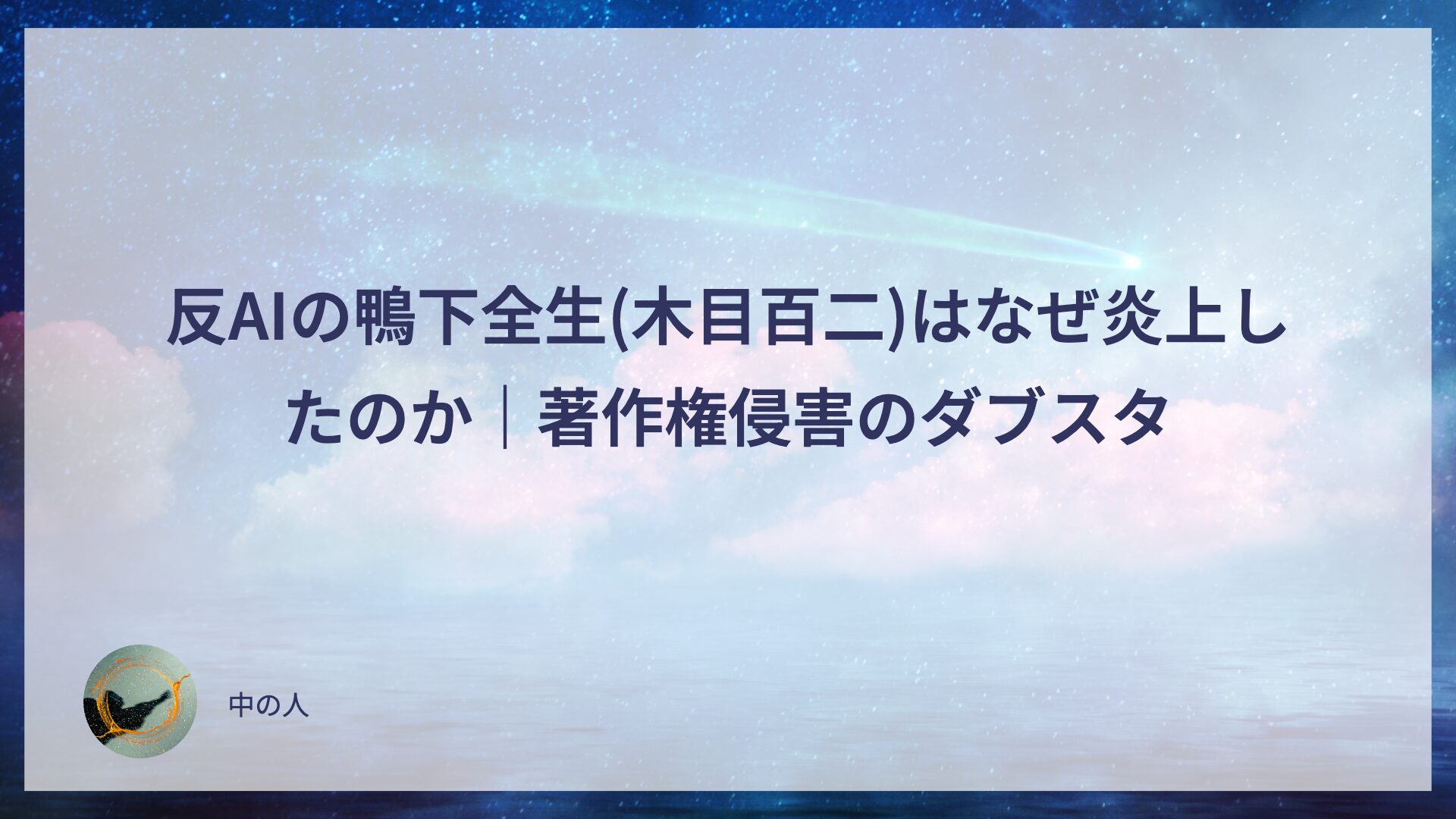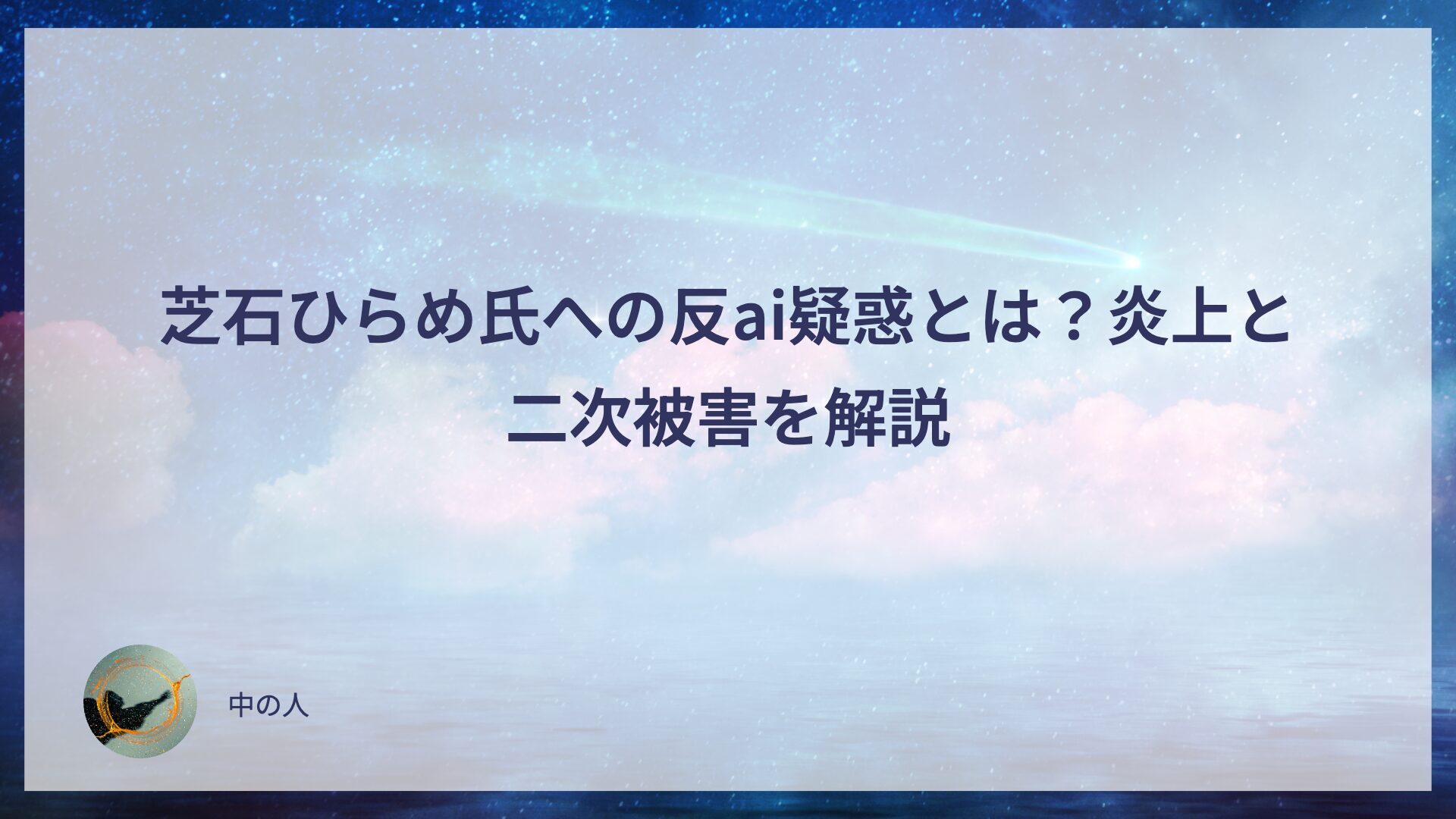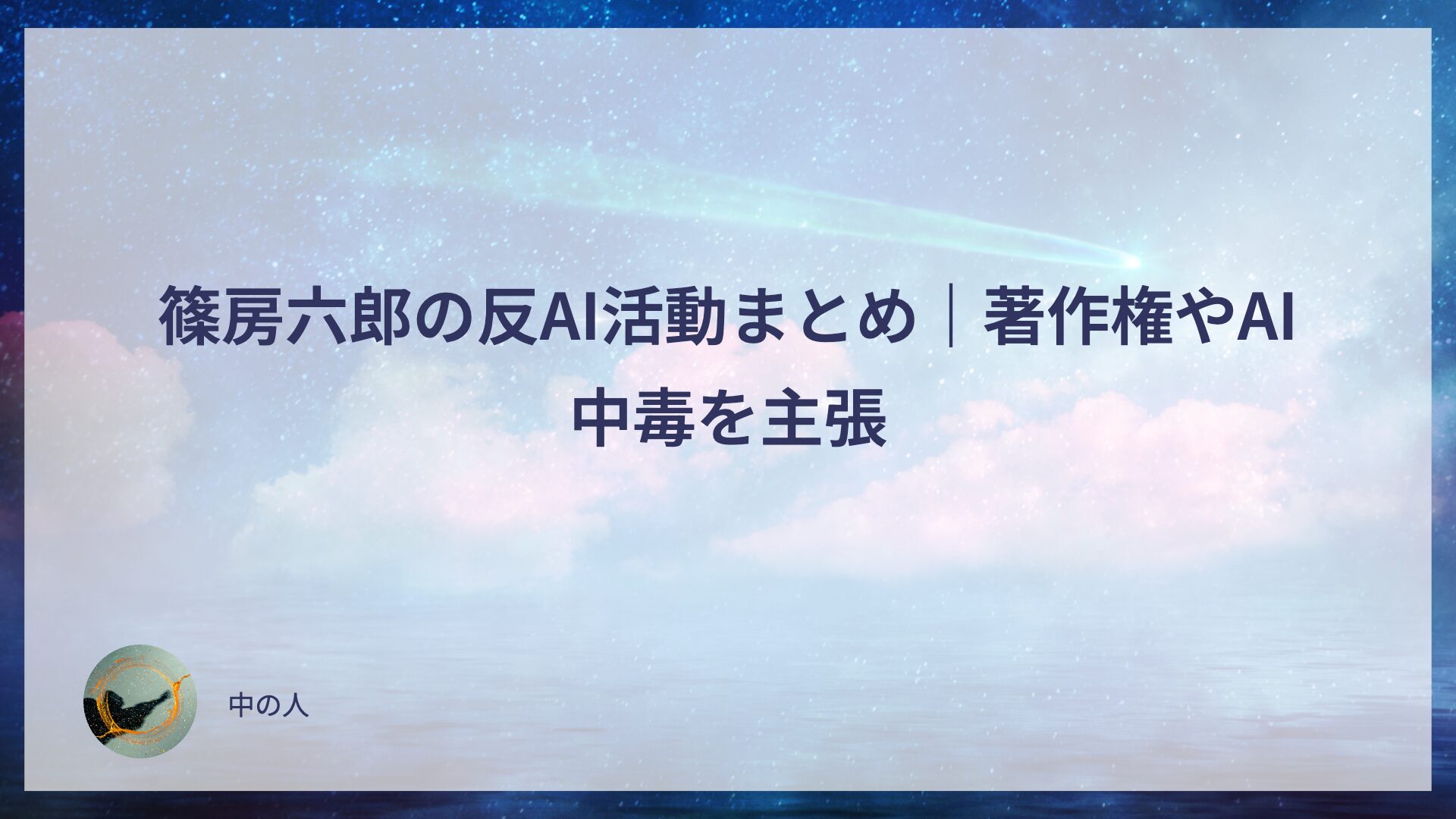反AIに対するなんj・5ch・togetterの反応まとめ!パブコメの結果と論争の背景を徹底解説
この記事では反AIに対するなんJ・5ch・togetterの反応や、注目されたパブリックコメントの結果について解説します。記事を読むことで、生成AIを巡る論争の背景や法的な解釈を客観的に理解できます。

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
反AIに対するなんJ・5ch・togetterの反応

反AIに対するなんJユーザーたちのリアルな反応を見ていきましょう。
- パブコメ結果は「当然」の声
- 過激な言動への冷ややかな視線
- ダブスタを指摘する声が多数
パブコメ結果は「当然」の声
反AI派の人たちが文化庁に提出したパブリックコメントでは、具体的に法律を改正するまでには至りませんでした。この結果に対してネット掲示板のなんJなどでは比較的冷静な反応が多く見られました。なんJユーザーの具体的な反応は以下のとおりです。
- 「まあそうなるだろう」
- 「法律的に考えれば当然の帰結」
- 「お気持ち表明で法律は動かない」
- 「数だけ集めても意味がない」
ネット上の議論に慣れ親しんだユーザーたちは、感情論と法的な議論を切り分けて考える傾向があるのかもしれません。
過激な言動への冷ややかな視線

反AI活動の一部で見られる過激な言動は、なんJでは冷ややかに見られています。特定のクリエイターをAI使用者と決めつけて攻撃する「魔女狩り」や、企業への誹謗中傷といった行為は、支持を得られていません。
むしろ「こんな面白いやつらなんで消す必要あるんや?」といったように、一連の騒動をエンターテイメントとして消費するような動きも見受けられます。
「もうカルトやろ」と言った意見もあり、反AIの活動が常軌を逸していると見なす声もあります。
ダブスタを指摘する声が多数
反AIの主張に見られる矛盾点、いわゆるダブルスタンダード(ダブスタ)を指摘する声も多く上がっています。特に槍玉に挙げられるのが、二次創作との関係です。
二次創作も、元の作品の著作権者の許諾なく行われるグレーな創作活動です。その二次創作文化に身を置く人々が、AIの無断学習だけを「窃盗」と非難することに対し、「二次創作が権利主張は草生える」といった厳しいツッコミが入ります。
自分たちの創作活動の土台となっている部分を棚に上げて、AIだけを批判する姿勢は一貫性がないと指摘されています。
反AIがなんj・5ch・togetterで話題!パブコメで何が起きた?
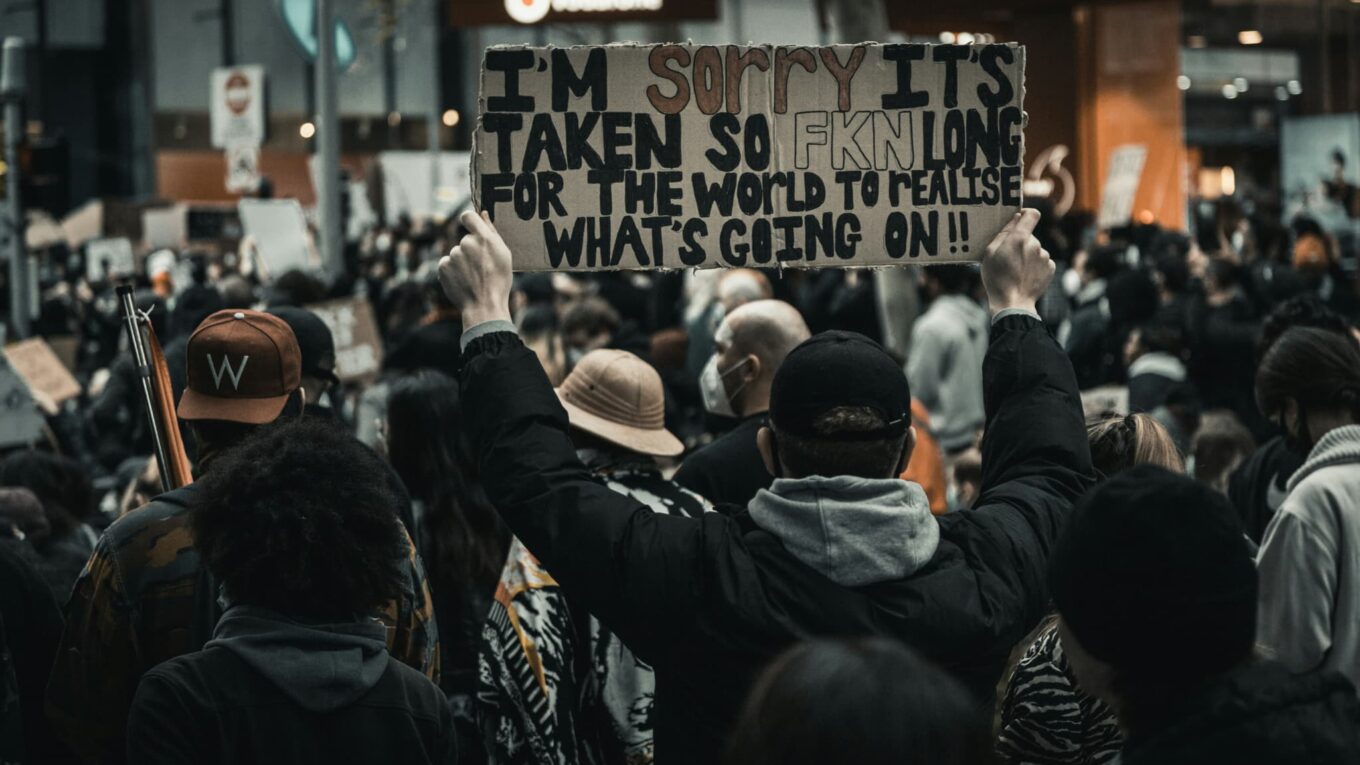
なんJでも大きな話題となったのが文化庁のパブリックコメントです。そもそもこの制度とは何か、なぜAIと著作権の問題で注目を集めることになったのか、その背景から見ていきましょう。
- そもそもパブリックコメントとは?
- なぜパブコメが注目されたのか
- パブコメの結果の要点まとめ
そもそもパブリックコメントとは?
パブリックコメントとは、国の行政機関が新しいルール(法律や政令など)を作る際に、事前にその案を公開し、国民から広く意見を募集する手続きのことです。行政運営の透明性や公正さを高める目的で導入されています。
この手続きは単なる人気投票や多数決ではありません。提出された意見の数が多ければ採用されるわけではなく、意見の内容にどれだけ説得力のある論拠や建設的な提案が含まれているかが重視されます。
集まった意見はすべて考慮された上で最終的なルールが決定され、その結果と意見に対する行政機関の考え方が公表されます。
なぜパブコメが注目されたのか

今回、パブリックコメントが大きな注目を集めたのは、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」の素案を公表し、国民の意見を求めたからです。生成AIの急速な普及に伴い、クリエイターの権利をどう守るべきか、社会的な関心が高まっていました。
このパブコメはAI開発を推進したい側と、クリエイターの権利保護を訴える反AI側の両者にとって、自分たちの意見を国の政策に反映させるための重要な機会となりました。
SNSなどを中心に意見提出の呼びかけが活発に行われ、最終的には約2万5千件もの意見が寄せられるなど、異例の注目度となったのです。この結果が、今後の日本のAI政策の方向性を占うものとして、大きな関心を集めました。
パブコメの結果の要点まとめ
文化庁はAIによる学習利用を日本の現行著作権法のもとで原則として認めるという見解を公式に発表しました。著作物を楽しむ目的でなければ、情報解析の一環として作者の許諾なく利用できると解釈されたのです。
つまり、反AI派が主張する「AIで作られた作品は著作権違反として罰するべき!」の意見は通らなかったということです。作品をAIだからと特別扱いせず、これまで通りの著作権のルールで対応されます。
反AI派が求めた多くの要望は採用を見送られる結果となりました。パブリックコメントの内容に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
» 反AIが提出したパブコメの結果と要点まとめ|なんjの反応・指摘された問題点も解説
AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。
今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。
- 仕事を奪われる
- 格差が広がる
- 思考停止してしまう
仕事が奪われる
「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。
- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ
- 俺は現場に出て働いているから関係ない
- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?
こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。
近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。
その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。
つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。
そうなってからやる気を出してももう遅いのです。
情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。
AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。
AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。
AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。
AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。
問題は「自分はどちら側に立つか」です。
思考停止してしまう
AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。
AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。
普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。
AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。
つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。
大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。
反AIの主張に見る論理と感情のズレ

なぜ反AIの活動は過激化するのでしょうか?ここからは3つの具体的な問題点を解説します。
- 大多数を占めた感情的な意見
- 著作権法そのものへの誤解
- 過激化する魔女狩りの実態
大多数を占めた感情的な意見
パブリックコメントに寄せられた約2万5千件の意見のうち、反AI派からのものの多くは、法的な論拠よりも感情的な訴えが中心でした。「クリエイターの長年の努力を無にする」「AI絵には魂がこもっていない」といった主張がその例です。
個人の心情としては理解できるものの、パブリックコメントは法律の解釈や制度設計に関する意見を求める場です。感情論に終始する意見は、残念ながら政策判断の材料として採用されにくい側面があります。
著作権法そのものへの誤解

反AI派の主張の中には、日本の著作権法を誤解していると思われる意見も多くありました。例えば「AIによる無断学習は違法な窃盗行為だ」という主張です。
これは、著作権法第30条の4で認められている「情報解析」目的の利用を考慮していない意見です。また「生成AIは元画像を切り貼りしている(コラージュのようなものだ)」という認識も、実際のAIの仕組みとは異なります。
AIは画像のパターンや特徴を数値データとして学習し、そこから全く新しい画像を生成します。元の画像をそのまま保存・利用しているわけではありません。こうした技術や法律への認識のズレが、議論がかみ合わない大きな一因となっています。
過激化する魔女狩りの実態
反AIが社会問題となっている背景には「AI魔女狩り」と呼ばれる現象が関係しています。AI魔女狩りとは手描きで制作されたイラストを、AIが生成したものではないかと一方的に決めつけ、集団で攻撃する行為を指します。
著名なイラストレーターであるあらいずみるい氏が被害に遭った事例は広く知られています。制作過程のデータを動画で公開し、手描きであることを証明した後も、一部のユーザーからの誹謗中傷はやみませんでした。
証拠を提示しても攻撃をやめない様子は、まさに中世の魔女裁判を彷彿とさせます。こうした行為は、クリエイターに大きな精神的ダメージを与える行為であり、自由な創作活動を萎縮させる深刻な問題です。
AI魔女狩りに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。
» 反AIの魔女狩りはなぜ起こる?背景にある嫉妬と暴走の心理
まとめ
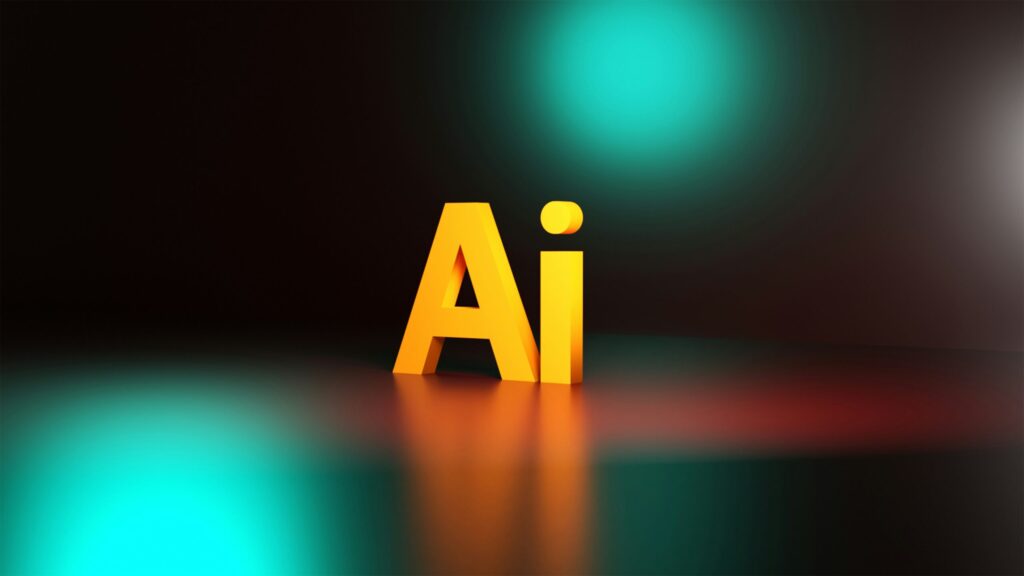
ネット掲示板なんJでは、反AIの感情論や過激な行動に冷ややかな意見が目立ちます。文化庁のパブリックコメントへの回答も、現行法に基づきAI学習を原則容認する内容でした。感情的な対立や法的な誤解を乗り越え、技術を正しく理解し建設的に議論する姿勢が今後は重要になります。
- なんJでは反AIの感情論に冷ややかな反応が多い
- 文化庁は現行法に基づきAI学習を原則容認
- 反AIの主張には法解釈の誤解が見受けられる
- AIとの共存には冷静で建設的な議論が不可欠