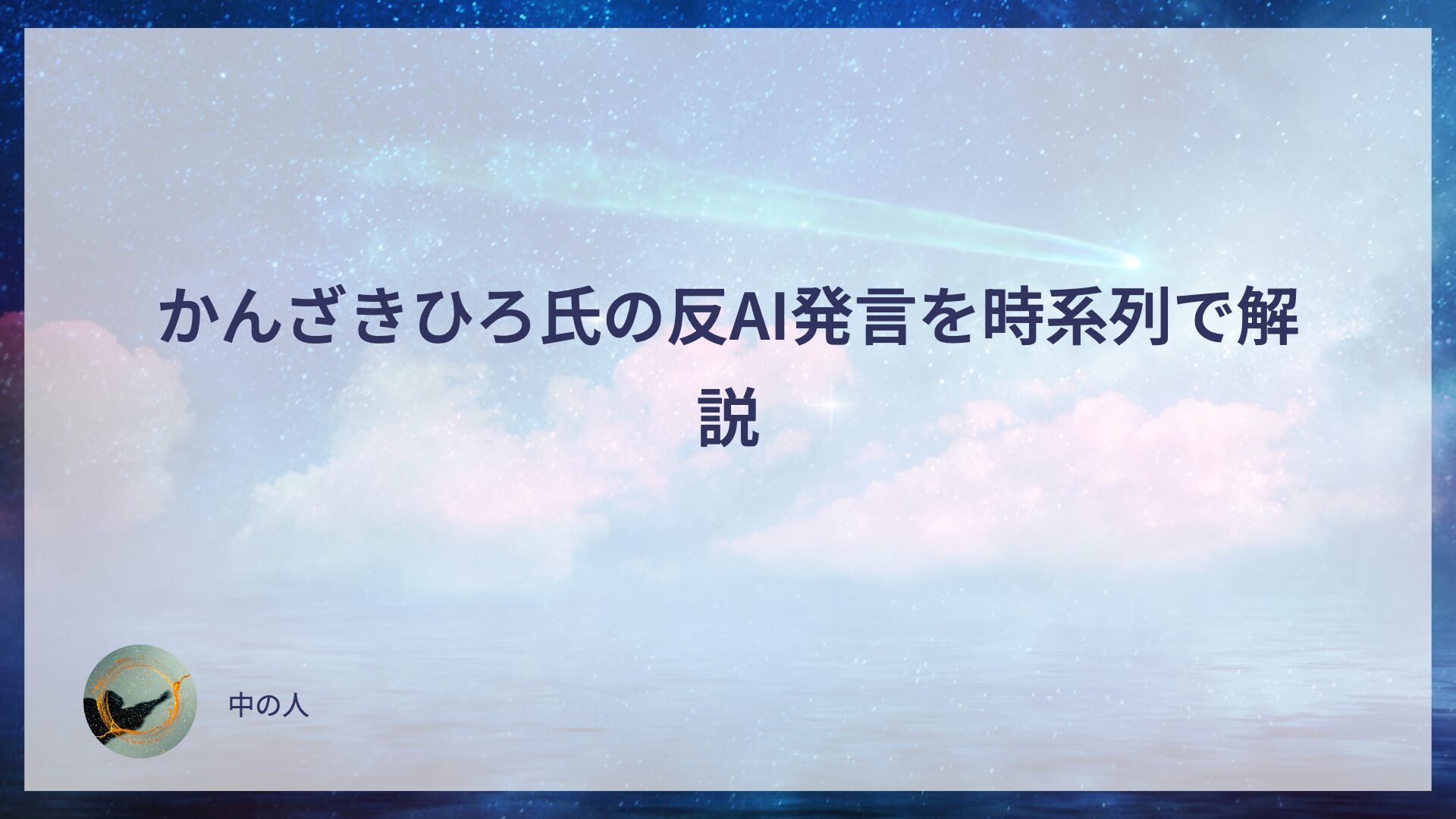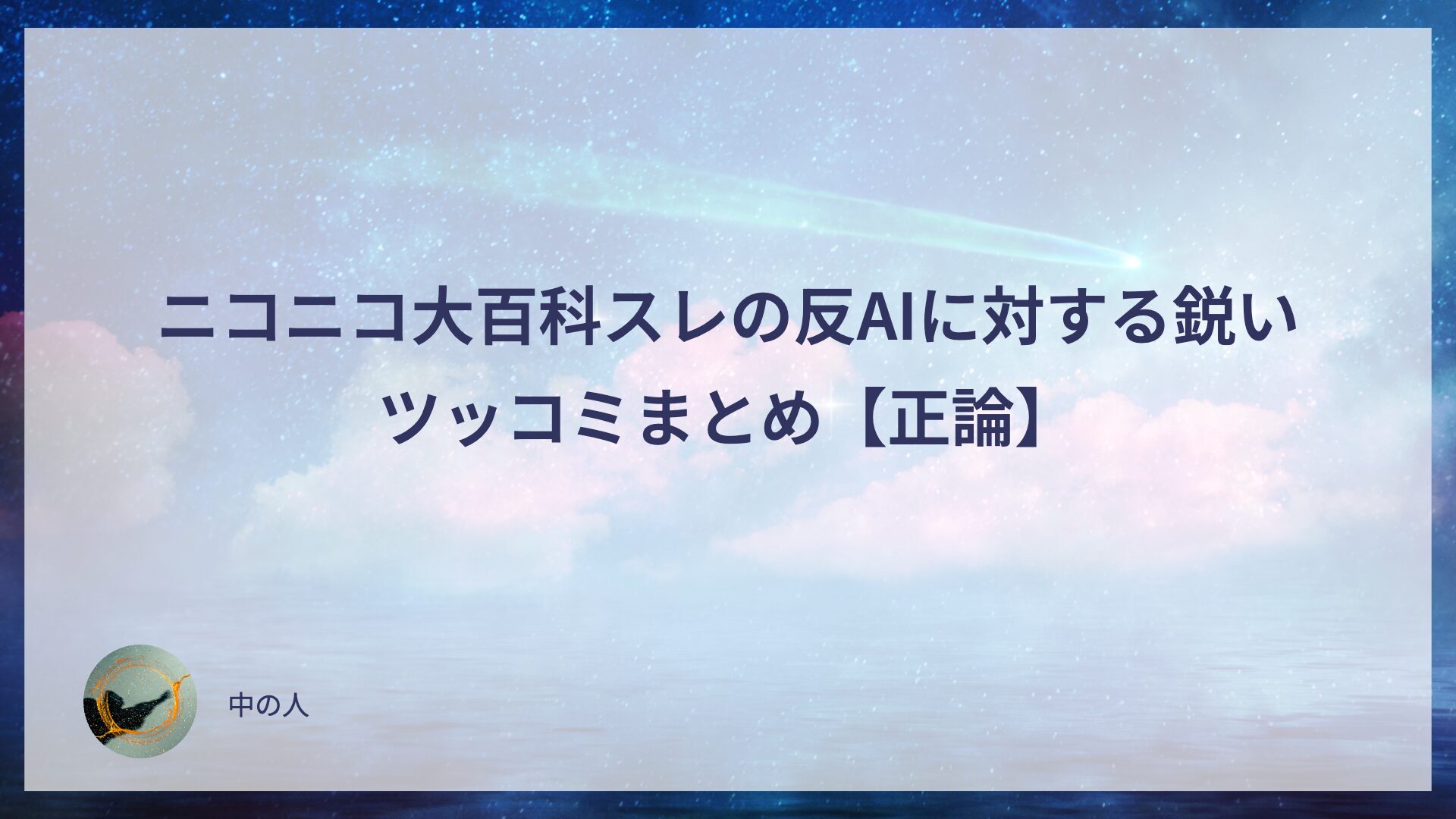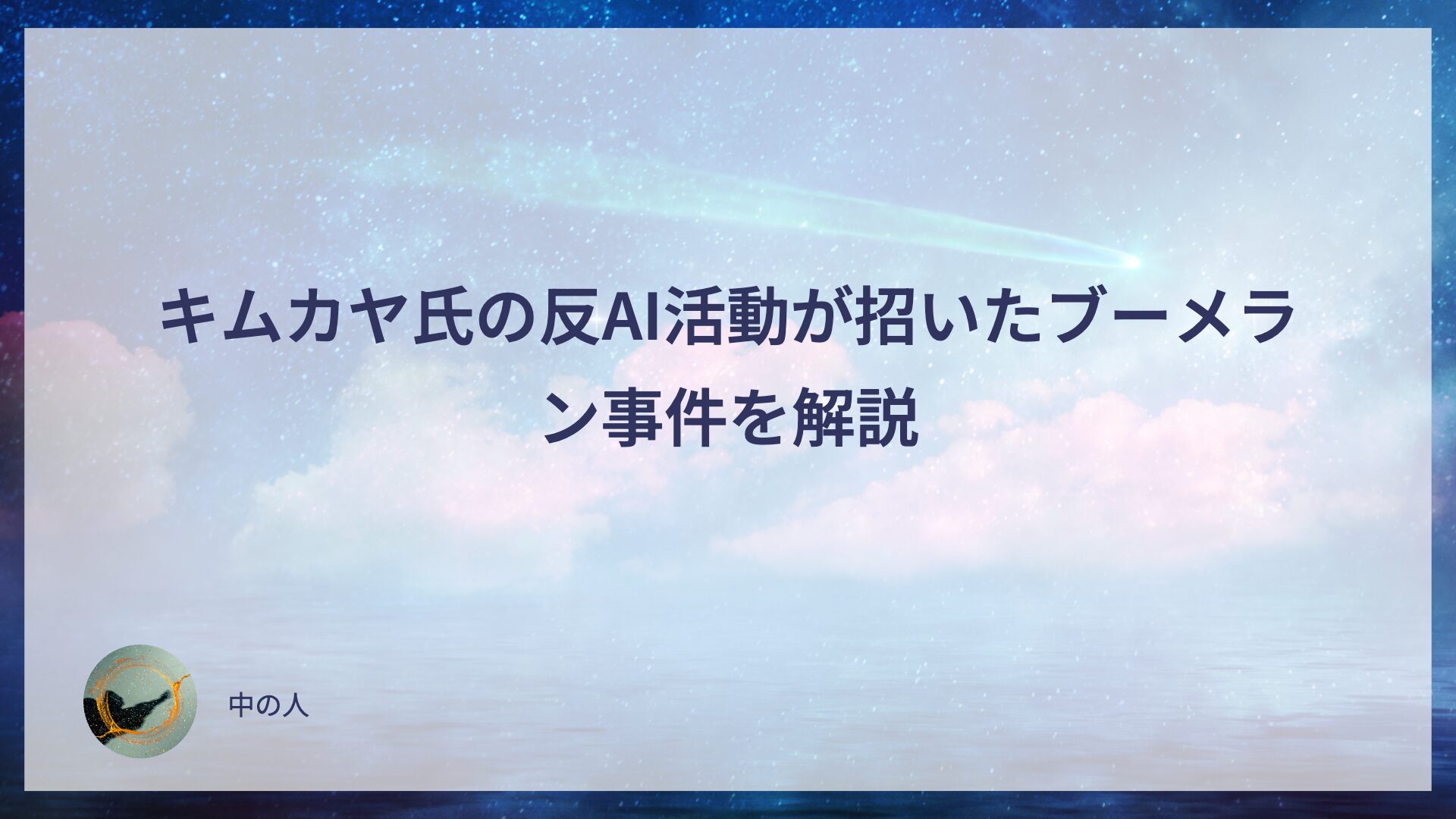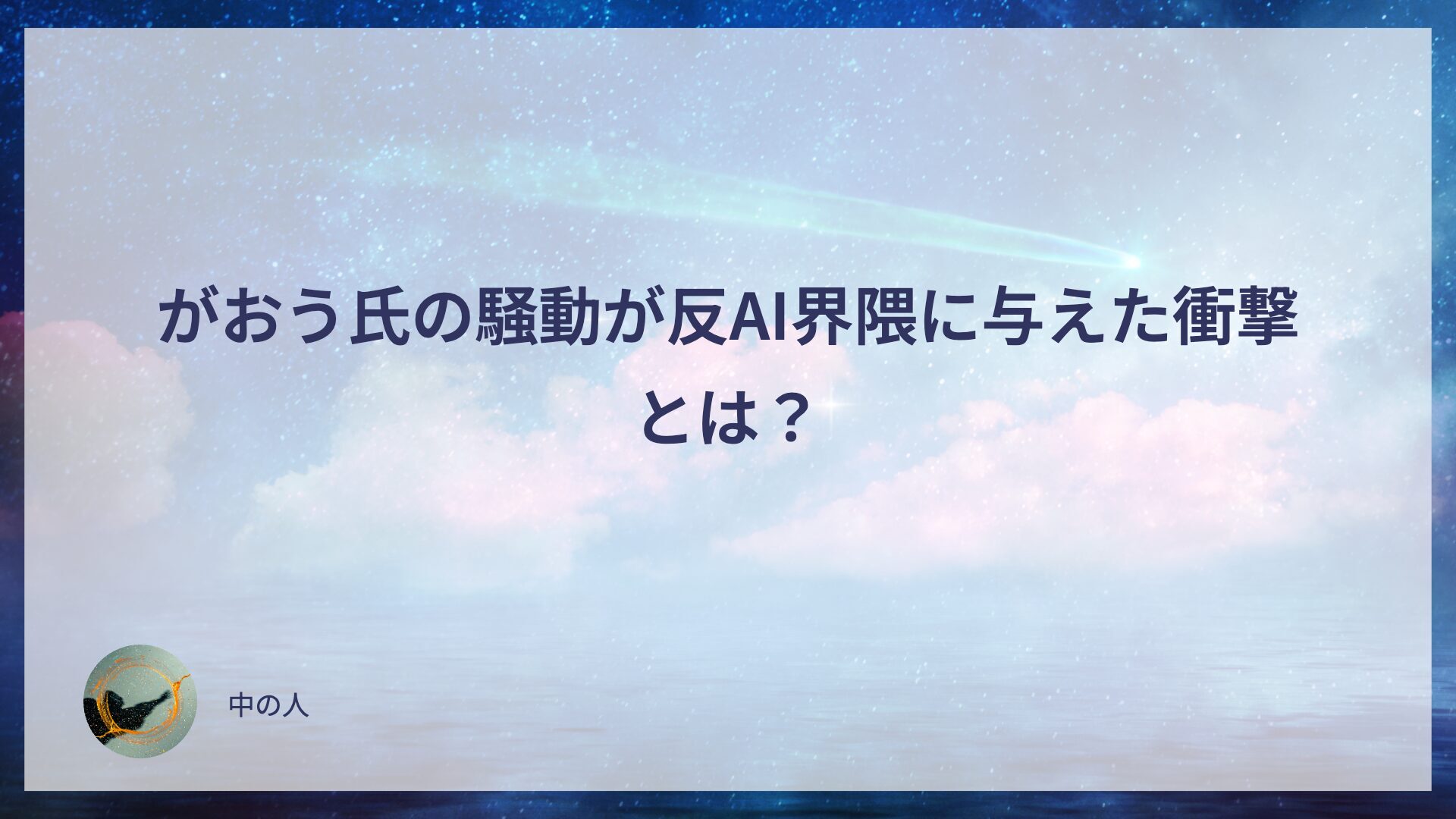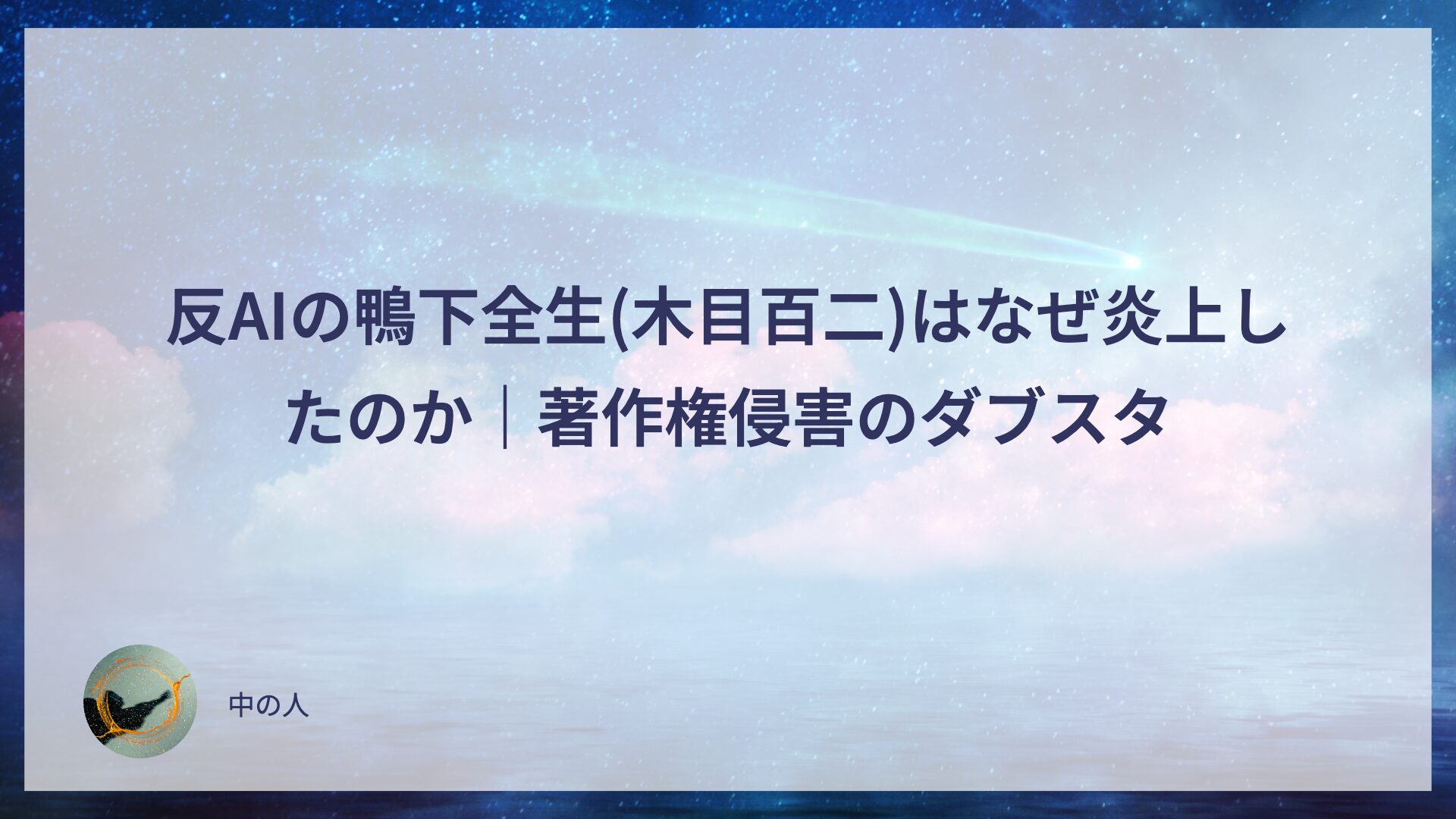反AIの「お気持ち表明」が響かない3つの理由|感情論の問題点を解説
この記事では「お気持ち表明」と言われている反AIの主な主張内容と、その感情論が社会に響かない理由を解説します。記事を読むことで反AI派の言動の背景にある問題点を客観的に理解できるでしょう。
感情論と建設的な議論の違いを知ることが、AIとクリエイターの問題を考える第一歩になります。

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
「お気持ち表明」と言われる反AIの主張

「お気持ち表明」と言われる反AIの主張について以下の内容を解説します。
- 「盗用」という言葉への固執
- 権利侵害の感情的な訴え
- クリエイターの尊厳という主張
- 技術進化への漠然とした不安
「盗用」という言葉への固執
反AIの人は「盗用」という言葉を頻繁に使いますが、この言葉こそ感情論と言われる理由です。AIの学習プロセスを理解していないため、反AI派の主張は「お気持ち表明」の一言で片付けられてしまうのです。
AIの学習プロセスは膨大なデータから画風のパターンを数学的に学習する仕組みです。この学習プロセスは人間が様々な作品から画風や表現方法を学ぶ過程に似ており「盗用」とは異なるものです。
「盗用」という強い言葉を使うことで、技術的な議論ではなく、相手を倫理的に非難する構図が生まれます。しかし、法的な根拠や技術的な理解がない非難は、建設的な対話にはなりません。
権利侵害の感情的な訴え

反AIの主張の根幹には「自分の絵が勝手に使われる」という権利侵害への感情的な訴えがあります。自分の作品が意図しない形で利用されることへの不快感や不安は、クリエイターとして自然な感情といえるでしょう。
この主張は、多くのクリエイターの共感を呼びやすいです。彼らは作品を守りたいという一心で声を上げていますが、現行法や技術の枠組みとどう向き合うのかという視点がなければ、単なる感情論に留まってしまいます。
「無断で学習されたくない」という感情は「学習されない権利」という法的な主張に直結しません。感情的な不快感の表明だけでは、法整備やルール作りといった具体的な解決策に向けた議論に進展させることが難しいのです。
クリエイターの尊厳という主張
「AIはクリエイターの努力や尊厳を踏みにじるものだ」という主張も、反AIの感情的な側面を強く反映しています。長年の鍛錬によって培われた技術や感性が、AIによって簡単に模倣されてしまうことへの危機感が背景にあります。
手描きの温かみや、作品に込められた魂といった価値が、AIによって軽んじられることへの憤りが、この主張の根底にあるのです。
しかし、この「尊厳」という主張は主観的で、客観的な基準では測れません。デジタル作画ツールが登場した際にも、同様の議論がありました。新しい技術が既存の価値観に挑戦するのは歴史上繰り返されてきたことです。
技術進化への漠然とした不安

生成AIという新しい技術そのものに対する漠然とした不安や恐れもあります。未知の技術が社会や自身の創作活動にどのような影響を与えるのか分からないという点が、強い拒否反応につながっています。
AIが人間の仕事を奪うのではないか、創作の価値を根本から変えてしまうのではないか、といった将来への懸念は多くの人が感じています。クリエイターにとっては、自身のアイデンティティに関わる問題であり、不安を感じるのは当然です。
ただ、不安という感情だけでは、建設的な議論は生まれません。技術のメリットとデメリットを冷静に分析し、リスクを管理しながら社会にどう実装していくかという視点が必要です。
「お気持ち表明」が社会に響かない3つの大きな理由

「お気持ち表明」が社会に響かない理由は以下のとおりです。
- 現行法と議論のズレ
- 技術に対する理解不足
- 矛盾するダブルスタンダード
現行法と議論のズレ
反AIの主張が理解されにくい大きな理由の一つに、日本の現行著作権法との間に存在するズレが挙げられます。日本の著作権法第30条の4では、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
〜中略〜
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
AI開発のための学習データとしての利用は、著作権法第30条の4に該当すると解釈されるのが一般的です。つまり「自分の作品をAIに学習させない権利」は、現行法上では保障されていません。
もちろん、法律が絶対的なものではなく、時代に合わせて改正されるべきだという議論は重要です。しかし、現行法を無視して一方的に違法だと断定する姿勢は、法治国家における議論の進め方として適切ではありません。
法的な土台を欠いた主張は単なる感情論と見なされ、説得力を持つことが難しいのです。
技術に対する理解不足

AI技術に対して誤解していることも、反AIの意見が広く受け入れられない理由の一つです。生成AIの仕組みを正しく理解しないまま、不正確な情報を基に批判を展開しているのです。
代表的な例として「AIは画像を切り貼りして合成している(コラージュのようなもの)」というものがあります。実際の生成AIは元画像を記憶・保存しているわけではありません。
このような技術的な実態を無視して「AIは泥棒だ」と非難することは、議論の前提が食い違っている状態を生み出します。技術を理解している人々から見れば、その主張は的外れなものに映ってしまいます。
矛盾するダブルスタンダード
反AIを掲げる人々の言動に見られる矛盾、いわゆる「ダブルスタンダード」も主張が受け入れられない要因です。自分たちの都合に合わせて基準を使い分けているため、社会的な支持を得にくくなっています。
具体例として、X(旧Twitter)の利用が挙げられます。Xの利用規約には、投稿されたコンテンツがAIの学習に利用される可能性がある旨が明記されています。
規約に同意してプラットフォームを利用しながら、プロフィール欄で「AI学習禁止」と宣言する行為は、行動と言動が一致していません。
二次創作活動を行っているクリエイターが、AIによる学習には厳しく反対する姿勢も矛盾しています。二次創作自体、原作の著作権に対してグレーな活動です。その一方で、AIに対しては完全なクリーンさを求める態度は、ダブルスタンダードと受け取られても仕方がないでしょう。
AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。
今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。
- 仕事を奪われる
- 格差が広がる
- 思考停止してしまう
仕事が奪われる
「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。
- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ
- 俺は現場に出て働いているから関係ない
- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?
こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。
近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。
その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。
つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。
そうなってからやる気を出してももう遅いのです。
情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。
AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。
AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。
AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。
AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。
問題は「自分はどちら側に立つか」です。
思考停止してしまう
AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。
AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。
普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。
AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。
つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。
大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。
反AI派の過激な言動

ここからは反AI自身の過激な言動が、いかにして運動全体の信頼性を損なっているのか解説します。
- デマの拡散と情報リテラシー
- AIユーザーへの過度な攻撃
- 界隈外への排他的な姿勢
デマの拡散と情報リテラシー
反AI運動の信頼性を著しく損なっているのが、不正確な情報やデマの拡散です。感情的な不安を煽る情報が、SNSを通じて検証されることなく広まってしまう現状があります。
例えば「Xの規約が特定の日付から変更され、AI学習が始まる」といった情報が拡散されたことがありました。実際には、以前から規約には同様の内容が含まれており、日付を特定した情報はデマでした。
また、「特定の設定をオフにすれば学習されない」といった技術的に不正確な情報も散見されます。
こうしたデマはAIに対する漠然とした不安感を持つ人々の間で信じられやすく、急速に拡散する傾向があります。しかし、一度デマだと判明すると、発信者やそのコミュニティ全体への信頼は大きく失われます。
情報リテラシーの欠如が反AI運動が非科学的で感情的な集団であるという印象を強めてしまっているのです。
AIユーザーへの過度な攻撃

反AIの過激な言動はAIを利用する個人への過度な攻撃や人格否定にまでエスカレートしています。誹謗中傷や集団での攻撃といった形をとることも多いです。本人たちにそのような意識はないと思いますが、結果的にそうなっているのが問題なのです。
「AI絵師」や「AI堕ち」といった呼び方でAIで作品を生成する人々を一方的に非難する傾向があります。
企業がプロモーションにAI画像を少し利用しただけでSNSで集中的に攻撃し、謝罪や投稿削除に追い込む「キャンセルカルチャー」的な動きも問題視されています。
特定の技術を利用するだけで個人を攻撃する姿勢は、社会的に認められるものではありません。このような過激な言動が反AI全体のイメージを悪化させているのです。
界隈外への排他的な姿勢
反AI派の議論は界隈内でのみ通用する独自のルールや価値観にもとづいていることが多いです。「ウォーターマークを入れるべき」「AI学習反対の意思表示をすべき」といった同調圧力が働き、それに従わない人を批判する風潮があります。
社会全体でAIとどう向き合うかという大きなテーマにおいて、特定のコミュニティの論理だけで話を進めようとすると、他分野の専門家や一般層との対話が成立しません。
まとめ
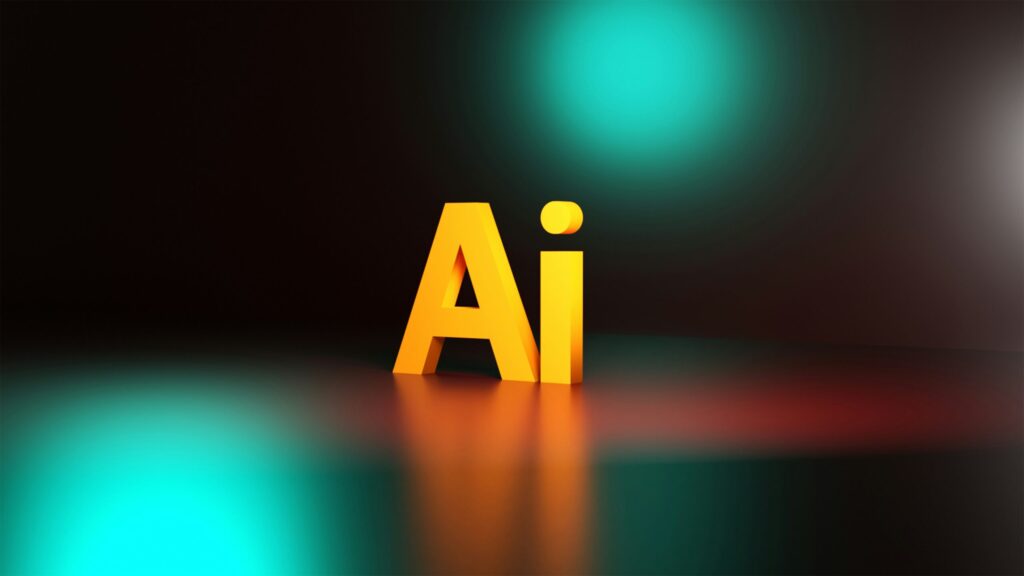
この記事では「反AIのお気持ち」表明がなぜ社会に響かないのかを解説しました。主な理由として、法や技術への理解不足、主張と行動の矛盾が挙げられます。「盗用」という言葉の誤用や過激な言動は、建設的な対話を妨げ、主張の信頼性を損なっています。