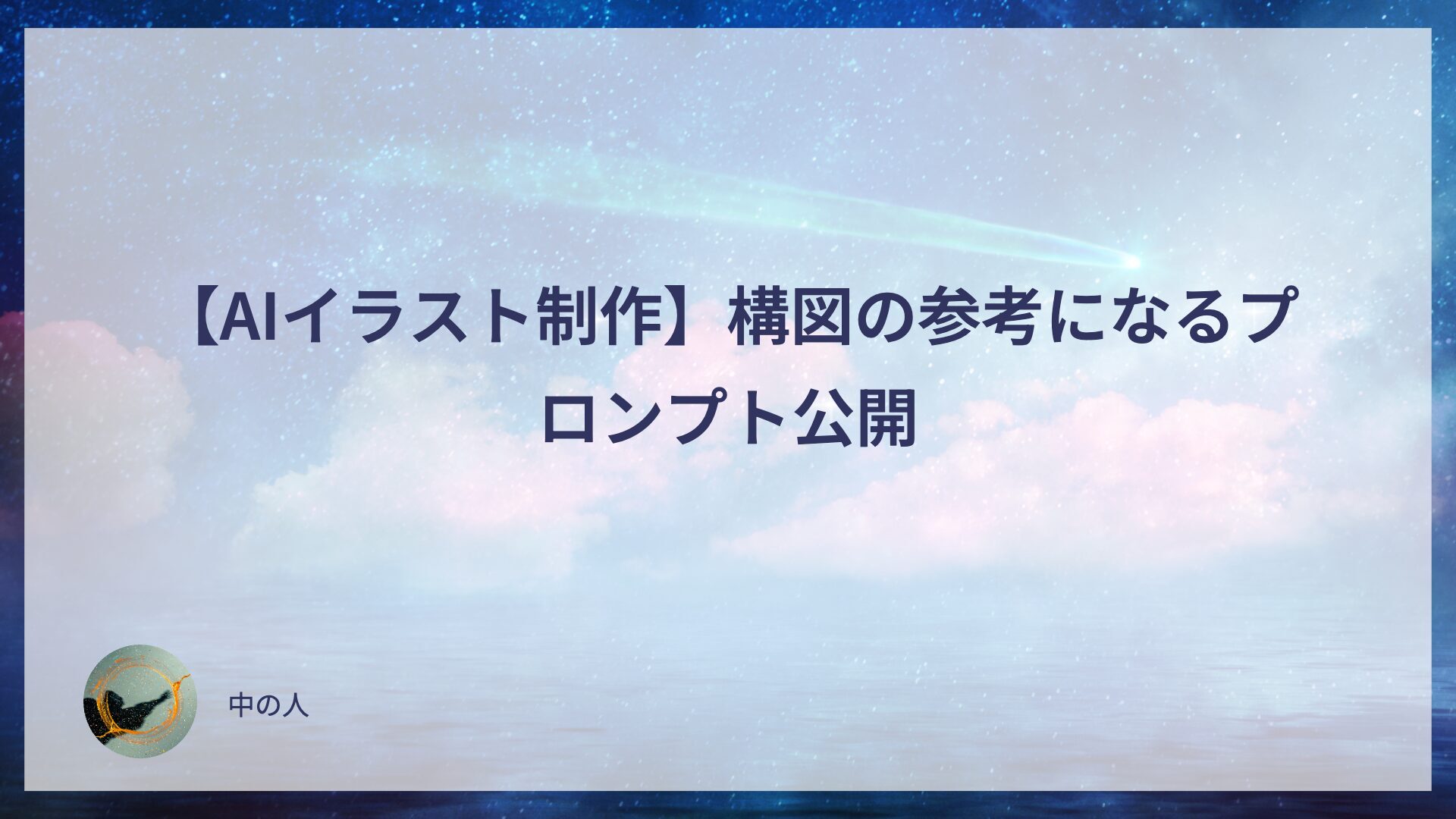AIイラスト販売は違法?著作権侵害の条件と安全な稼ぎ方を解説

「AIイラストを販売してみたいけれど、違法だったら嫌だな」と不安に感じていませんか?この記事ではAIイラスト販売が違法になるケースや著作権侵害の条件、リスクを避けて安全に収益化する方法を解説します。
記事を読めば法律の知識がなくてもトラブルを未然に防ぐポイントが分かり、安心してAIイラスト販売を始められます。
- AIイラスト販売が合法か違法かの判断基準
- 著作権侵害と見なされる「類似性」と「依拠性」の具体的な意味
- トラブルを避け、安全にAIイラストを販売するための実践的な方法
- AI時代におけるクリエイターの役割と未来の可能性
AIイラスト販売は違法?著作権侵害の境界線

ここではAIイラスト販売の合法性や著作権侵害の基準、そして過去の事例について、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。
- AIイラスト販売そのものは合法
- 著作権侵害となる2つの条件
- 「画風を真似るだけ」はセーフ?
- AI生成物に著作権は発生しない
- 実際にあった書類送検の事例
AIイラスト販売そのものは合法
AI(人工知能)で生成したイラストを販売する行為自体は、現在の日本の法律で禁止されていません。誰でもAIツールを使ってイラストを作成し、それを販売して収益を得ることが可能です。
ただし、どのようなイラストでも無条件に販売して良いわけではありません。販売するイラストが他人の権利を侵害している場合、違法になる場合があります。
特に注意が必要なのが「著作権」と、わいせつな表現などに関する「刑法」です。
安全にAIイラスト販売を行うためには、何が許可されていて、何が問題になるのか、その境界線を正しく理解しておく必要があります。
著作権侵害となる2つの条件

AIイラストが著作権侵害と判断される条件は「類似性」と「依拠性」です。
類似性とは生成されたAIイラストが、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるほど似ている状態を指します。
雰囲気が似ているだけでは認められず、キャラクターデザインの具体的な特徴や構図などが酷似している場合に問題となります。
依拠性とは「他人の著作物をもとにして創作した」という意味です。既存のイラストや写真などを参考にしたうえで、AIイラストを生成した場合に認められます。
全くの偶然で似た作品が生まれた場合には、依拠性はないと判断されます。AIに特定のキャラクター名を指示して生成した場合、依拠性が認められる可能性は高まります。
どちらか一方だけでは著作権侵害が成立しません。例えば元の作品を全く知らずに偶然似たものができてしまった場合や、参考にはしたけれど全く似ていない作品になった場合は、問題になりません。
この二つの要素が揃ったとき、著作権侵害とみなされるリスクが生じます。
「画風を真似るだけ」はセーフ?
特定の作家の「画風」や「作風」を真似てAIイラストを生成した場合、それだけで直ちに著作権侵害となる可能性は低いです。
日本の著作権法が保護しているのは、キャラクターのデザインや背景といった「具体的な表現」です。一方で、画風やアイデア、タッチといった抽象的なスタイルそのものは、著作権の保護対象外とされています。
とはいえ、有名作家の名前を挙げて「〇〇先生風」のように宣伝したり、画風を模倣した結果、特定のキャラクターと酷似したイラストが生成されたりした場合は注意が必要です。
著作権侵害とはならなくても、別の法律に抵触したり、倫理的な観点からトラブルに発展したりする可能性があります。
AI生成物に著作権は発生しない

現在の日本の法律の考え方では、AIが自動的に生成しただけのイラストには、原則として著作権は発生しません。
著作権は人間の「思想や感情を創作的に表現したもの」に対して認められる権利です。AI生成したイラストに人間の創作的な意図が介在しない場合、その生成物は「著作物」には該当しないと解釈されています。
あなたがAIで生成したイラストを他人が無断でコピーして使ったとしても、著作権侵害を主張するのが難しいことを意味します。逆に、他人が生成したAIイラストと偶然同じものができても、基本的には問題になりません。
実際にあった書類送検の事例
AIイラストが関連する事件として、生成AIで作った女性のわいせつな画像を印刷した枕カバーを販売した男性が、わいせつ物頒布等の疑いで書類送検された事例があります。
この事件はAIイラストの「著作権侵害」が直接の原因ではありません。問題となったのは、生成されたイラストの内容が刑法に触れる「わいせつ物」にあたると判断された点です。
この事例から分かるように、AIイラストを販売する際のリスクは著作権だけではありません。生成するコンテンツの内容そのものが法律や公序良俗に反していないかどうかも、常に意識する必要があります。
合法的にAIイラストを販売する方法

合法的にAIイラストを販売する方法は以下のとおりです。
- 商用利用OKなAIツールを選ぶ
- 「AI生成作品」の明記は必須
- 特定の作品に似せない意識
- AI利用禁止のサイトに注意
商用利用OKなAIツールを選ぶ
安全にAIイラストで収益を上げるためには、利用規約で商用利用が許可されているAIツールを選ぶことが重要です。
多くのAI画像生成ツールには無料プランと有料プランがあり、商用利用の可否が異なります。例えば画像生成AIツールの「Midjourney」は、有料プランに加入すれば商用利用が可能ですが、無料版での利用は認められていません。
ツールを選ぶ際には、
- 商用利用が可能か
- 収益額に上限はあるか
- クレジット表記は必要か
といった点を、必ず公式サイトの利用規約で確認しましょう。著作権処理済みのクリーンなデータで学習していることを特徴とする「Adobe Firefly」のようなツールを選ぶのも、リスクを低減する一つの方法です。
「AI生成作品」の明記は必須

AIで生成したイラストを販売する際には、商品説明などで「AI生成作品である」ことを明確に記載することをおすすめします。
この表記は、購入者との不要な誤解やトラブルを防ぐために有効です。購入者は、作品がAIによって作られたことを理解したうえで購入を判断できます。
BOOTHやココナラといったイラスト販売プラットフォームの中には、利用規約でAI生成作品の明記を義務付けている場所もあります。プラットフォームのルールを守り、誠実な姿勢で販売活動を行うことが、長期的な信頼につながります。
特定の作品に似せない意識
著作権侵害のリスクを根本から避けるために最も重要なのは、特定の作品に似せないという強い意識を持つことです。
AIに指示を出すプロンプトを入力する際に、既存のアニメやゲームのキャラクター名、作品名、作家名などを直接使うのは絶対に避けるべきです。
たとえ「〜風」という言葉を付け加えたとしても、依拠性が認められ、類似性の高いイラストが生成されれば著作権侵害と判断される可能性があります。
目指すべきは、AIというツールを使って自分だけのオリジナルキャラクターや世界観を創り出すことです。
AI利用禁止のサイトに注意

全てのプラットフォームがAI生成物の販売を歓迎しているわけではありません。AIによる生成作品の出品を明確に禁止しているサイトも存在します。
代表的な例として、クリエイターへのリクエストサービス「Skeb」が挙げられます。Skebは利用規約でAI生成物の納品を禁止しており、違反した場合はアカウント停止などの厳しい措置が取られます。
プラットフォームごとにAIへのスタンスは大きく異なります。販売を始める前には必ずそのサイトの利用規約やガイドラインを熟読し「AI生成作品の取り扱い」に関する項目を確認してください。ルールを無視した出品は、トラブルの原因となります。
AI絵師の始め方と収益化の方法については以下の記事で解説しています。
» AI絵師のやり方を完全解説!おすすめ無料ツールや収益化まで網羅的に紹介
クリエイターがAI時代を生き抜くための5つの戦略

変化の時代を乗りこなし未来を切り拓くために、クリエイターが今からできることを5つの視点で考えてみましょう。
- AIを創作活動に活用する
- 独自のブランドを形成する
- 共感を生む「物語」を作る
- 一つのスキルに固執しない
- 基礎的なスキルを磨き続ける
AIを創作活動に活用する
AIは敵ではありません。AIを脅威と捉えるのではなく創作活動をサポートするツールと捉えることが大切です。作業の効率化や新しいアイデアのきっかけとしてAIを活用することで、創作活動がさらに楽しくなります。
AIには以下のような活用法があります。
- アイデア出し
- ラフ制作
- 背景や素材の制作
- 参考資料の調査
AIをアシスタントとして使いこなすことで、クリエイターはより創造性の高い部分に時間とエネルギーを集中させられます。技術を否定するのではなく賢く利用することで、作品のクオリティと生産性を向上させることが可能です。
独自のブランドを形成する

AI時代にクリエイターが活躍し続けるには「あなただからお願いしたい」と言われる強力な独自ブランドの形成が不可欠です。生成AIは特定の画風を模倣できても、作家自身の個性や作品に込めた世界観、クライアントとの信頼関係といった、属人的な価値までは再現できないからです。
独自の世界観を押し出すだけでなく、丁寧なコミュニケーションや確実な納期管理といったプロとしての姿勢も、AIにはない人間ならではの価値であり、強力なブランドの一部となります。
SNSやリアルでの交流の場を増やして、独自のコミュニティを形成するのもおすすめです。単なる「絵を描ける人」から脱却し、作品や活動全体でファンを魅了する、唯一無二の「クリエイターブランド」を確立しましょう。
共感を生む「物語」を作る
AIが生成したイラストと人間が描いたイラストの決定的な違いは、作品の背景にある「物語」です。人間は美しいイラストそのものだけでなく、その作品が生まれるまでのストーリーや、作者の想いにも心を動かされます。
- 作者がどのような経験をしてこのテーマにたどり着いたのか
- 制作過程でどのような苦労や発見があったのか
- この作品を通じて何を伝えたかったのか
これらの物語は作品に深みと共感を与え、ファンとの強い絆を育みます。AIが生成したイラストには、この人間的な文脈が存在しません。自身の活動や作品にまつわる物語をSNSで積極的に発信し、ユーザーとの関係性を築くことが重要です。
一つのスキルに固執しない

AIの台頭によってイラストレーション業界の構造は大きく変化していく可能性があります。説明のための挿絵や個性を問われない量産的なイラストの需要は、AIやフリー素材に置き換わっていきます。
イラストを描くという単一のスキルに固執せず、複数のスキルを掛け合わせて自身の価値を高める視点が重要です。イラストレーターとしての基礎能力を軸に、新たな分野へ挑戦することが生存戦略となり得ます。
Live2Dや3Dモデリングを学んでイラストを動かせるようになったり、デザインの知識を深めてより訴求力の高い制作物を作れるようになったりするのもおすすめです。自身の経験を活かしてイラストの描き方を教える講師になる道もあるでしょう。
基礎的なスキルを磨き続ける
AIの技術がどれだけ発達しようとも、クリエイターとしての活動の土台となるのは、自分自身が持つ専門的なスキルです。AIの性能を最大限に引き出して優れた作品を生み出すためには、使い手である人間のスキルが不可欠になります。
基本的なスキルがなければ、作品の良し悪しを正しく判断することすらできません。
- デッサンの知識がなければ人物の骨格の違和感を見抜けない
- 色彩理論を理解していなければ配色の良し悪しがわからない
AIは無数の選択肢を提示してくれますが、その中から最適解を選び出し、さらに洗練させていく「キュレーション能力」こそ人間にしかできない領域なのです。
AIがあるからといって自分のスキルを磨かないクリエイターは他の人と同じことしかできないため、残念ながら仕事を失うでしょう。AIに負けないためには基盤となるスキルを磨き続ける姿勢が何よりも重要です。
まとめ

AIイラストの販売はルールを守れば違法ではありません。大切なのは著作権侵害の境界線を理解し、他者の権利を尊重する姿勢です。基本的な注意点を守ることで、トラブルのリスクは大幅に減らせます。
AI絵師の始め方と収益化の方法については以下の記事で解説しています。
» AI絵師のやり方を完全解説!おすすめ無料ツールや収益化まで網羅的に紹介