AI絵師はなぜ嫌われる?うざい・頭おかしいと言われる理由を解説
この記事ではAI絵師が批判される著作権や倫理上の理由を解説します。対立の背景を理解することで、これからのクリエイターの生存戦略を考えるヒントが得られます。

- AIを使った副業に興味がある
- 自分に合った副業がわからない
- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい
こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。
「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。
AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。
これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。
AI絵師がうざい・頭おかしいと言われる理由

AI絵師がなぜこれほどまでに批判されるのでしょうか。その背景にある問題について解説していきます。
- 著作権と学習データの問題
- クリエイターの努力の軽視
- 一部利用者の過激な言動
- 表現の均質化への懸念
著作権と学習データの問題
AI絵師が批判される最も根深い原因の一つが、著作権と学習データの問題です。多くの画像生成AIは、インターネット上から膨大な数の画像を収集して学習に利用しています。AIのデータ収集には、制作者の許可を得ていないイラストや写真が多数含まれています。
クリエイター側から見れば自分の作品が知らないうちにいわば「エサ」としてAIに与えられ、自身の作風を模倣したイラストの生成に使われることになります。自身の作品を盗用されているのと同じだと感じる人が多く、強い反発を生んでいます。
日本の著作権法第30条の4ではAI開発を目的とした情報解析は、原則として著作権者の許諾なく行えるとされています。しかし、この法律はあくまで「思想又は感情を自ら享受する目的ではない場合」を想定したものです。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外とされており、この点の解釈は非常に曖昧です。法律とクリエイターの感情との間に大きな溝が存在する状態が、対立を深刻化させているのです。
クリエイターの努力の軽視

クリエイターが積み重ねてきた努力や技術が軽視されているように見える点も、AI絵師が嫌われる理由の一つです。AIは簡単な指示文(プロンプト)を入力するだけで、数秒から数分でクオリティの高いイラストを生成できてしまいます。
AI画像生成の手軽さが、人間のクリエイターの制作プロセスを飛び越えてしまうため「これまでの努力が踏みにじられている」と感じる人が多いのです。
完成した作品の質だけが評価され、そこに至るまでの試行錯誤や習熟の過程が無視される風潮は、創作活動の価値そのものを揺るがしかねないという懸念につながっています。そのため「AI絵師がうざい」という感情的な意見が出てしまいます。
一部利用者の過激な言動
一部のAI絵師は「もう絵師は不要になる」「AIを使えないのは時代遅れだ」といった挑発的な発言で、手描きのクリエイターを攻撃するケースが見受けられます。特定のクリエイターの作品を無断でAIに追加学習させてイラストを作成し、本人の目につく場所で公開するといった悪質な嫌がらせも問題になっています。
pixivのようなイラスト投稿サイトでは、AI生成作品であることを隠して投稿し、ランキングを埋め尽くしてしまう事態も発生しました。
このような著作権意識の低さやクリエイターへの敬意を欠いた振る舞いが、AIイラストという技術そのものへの不信感や嫌悪感を増幅させています。このような態度では「AI絵師が頭おかしい」と言われても仕方ありません。
表現の均質化への懸念
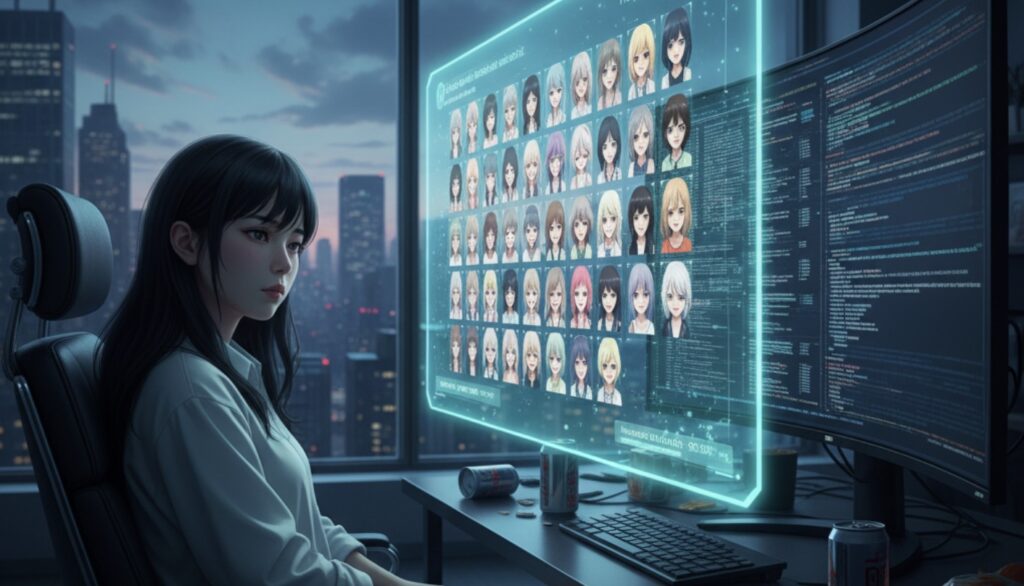
AIイラストがSNSや投稿サイトに溢れることで、表現の多様性が失われるのではないかという懸念も広がっています。生成AIから出力されるイラストはどれも画風が似通ってしまう傾向があります。
その結果「どこかで見たようなイラストばかりでつまらない」と感じるユーザーが増えてしまうのです。AIが生成するイラストは膨大なデータの平均から導き出された「それらしい」組み合わせであり、無機質に見えてしまうという意見も多いです。
多くの人が同じようなテイストの作品を大量に目にする状況は、クリエイティブな世界の刺激や面白さを損なわせる危険性があります。クリエイターの世界を根本的に破壊する可能性があるため、AI絵師は嫌われているのです。
クリエイターがAI時代を生き抜くための5つの戦略

変化の時代を乗りこなし未来を切り拓くために、クリエイターが今からできることを5つの視点で考えてみましょう。
- AIを創作活動に活用する
- 独自のブランドを形成する
- 共感を生む「物語」を作る
- 一つのスキルに固執しない
- 基礎的なスキルを磨き続ける
AIを創作活動に活用する
AIは敵ではありません。AIを脅威と捉えるのではなく創作活動をサポートするツールと捉えることが大切です。作業の効率化や新しいアイデアのきっかけとしてAIを活用することで、創作活動がさらに楽しくなります。
AIには以下のような活用法があります。
- アイデア出し
- ラフ制作
- 背景や素材の制作
- 参考資料の調査
AIをアシスタントとして使いこなすことで、クリエイターはより創造性の高い部分に時間とエネルギーを集中させられます。技術を否定するのではなく賢く利用することで、作品のクオリティと生産性を向上させることが可能です。
独自のブランドを形成する

AI時代にクリエイターが活躍し続けるには「あなただからお願いしたい」と言われる強力な独自ブランドの形成が不可欠です。生成AIは特定の画風を模倣できても、作家自身の個性や作品に込めた世界観、クライアントとの信頼関係といった、属人的な価値までは再現できないからです。
独自の世界観を押し出すだけでなく、丁寧なコミュニケーションや確実な納期管理といったプロとしての姿勢も、AIにはない人間ならではの価値であり、強力なブランドの一部となります。
SNSやリアルでの交流の場を増やして、独自のコミュニティを形成するのもおすすめです。単なる「絵を描ける人」から脱却し、作品や活動全体でファンを魅了する、唯一無二の「クリエイターブランド」を確立しましょう。
共感を生む「物語」を作る
AIが生成したイラストと人間が描いたイラストの決定的な違いは、作品の背景にある「物語」です。人間は美しいイラストそのものだけでなく、その作品が生まれるまでのストーリーや、作者の想いにも心を動かされます。
- 作者がどのような経験をしてこのテーマにたどり着いたのか
- 制作過程でどのような苦労や発見があったのか
- この作品を通じて何を伝えたかったのか
これらの物語は作品に深みと共感を与え、ファンとの強い絆を育みます。AIが生成したイラストには、この人間的な文脈が存在しません。自身の活動や作品にまつわる物語をSNSで積極的に発信し、ユーザーとの関係性を築くことが重要です。
一つのスキルに固執しない

AIの台頭によってイラストレーション業界の構造は大きく変化していく可能性があります。説明のための挿絵や個性を問われない量産的なイラストの需要は、AIやフリー素材に置き換わっていきます。
イラストを描くという単一のスキルに固執せず、複数のスキルを掛け合わせて自身の価値を高める視点が重要です。イラストレーターとしての基礎能力を軸に、新たな分野へ挑戦することが生存戦略となり得ます。
Live2Dや3Dモデリングを学んでイラストを動かせるようになったり、デザインの知識を深めてより訴求力の高い制作物を作れるようになったりするのもおすすめです。自身の経験を活かしてイラストの描き方を教える講師になる道もあるでしょう。
基礎的なスキルを磨き続ける
AIの技術がどれだけ発達しようとも、クリエイターとしての活動の土台となるのは、自分自身が持つ専門的なスキルです。AIの性能を最大限に引き出して優れた作品を生み出すためには、使い手である人間のスキルが不可欠になります。
基本的なスキルがなければ、作品の良し悪しを正しく判断することすらできません。
- デッサンの知識がなければ人物の骨格の違和感を見抜けない
- 色彩理論を理解していなければ配色の良し悪しがわからない
AIは無数の選択肢を提示してくれますが、その中から最適解を選び出し、さらに洗練させていく「キュレーション能力」こそ人間にしかできない領域なのです。
AIがあるからといって自分のスキルを磨かないクリエイターは他の人と同じことしかできないため、残念ながら仕事を失うでしょう。AIに負けないためには基盤となるスキルを磨き続ける姿勢が何よりも重要です。
まとめ

AI絵師が嫌われる背景には、著作権や努力の価値を巡る根深い問題があります。しかし、技術の進歩は止められません。AIをツールとして活用し、人間ならではの「物語」や共感を武器にすることが、今後のクリエイターにとって重要になるでしょう。








